お盆の夜、僕たちは毎年恒例の盆灯籠流しをするため、海辺へと向かった。
照りつける夏の日差しも沈み、海は静かに波を立てている。
月明かりがかすかに海面を照らし、灯籠がゆっくりと漂う姿を想像していた。
「よし、みんなで流そう」
友人のケンが声をかけ、僕たちはそれぞれの灯籠に火を灯した。
穏やかな夜風に揺られ、灯籠の光は幻想的に海面に映り込んだ。
「これでご先祖様も無事に戻れるね」
僕たちは軽い冗談を交わしながら、灯籠を海に流し始めた。
灯籠は緩やかに沖へ向かっていく。
潮の流れは穏やかで、何の問題もないように思えた。
だが、しばらくすると、異変が起きた。
「あれ、戻ってきてるぞ…」
最初に気づいたのはケンだった。
確かに、沖へ向かっていたはずの灯籠が、なぜかこちらに向かって逆流してきていた。
まるで海が吐き出すように、灯籠が次々と岸に戻ってくる。
「なんだよ、気味悪いな…」
誰かが不安げに呟いた。
灯籠が岸に近づくにつれて、何とも言えない冷気が漂ってきた。
夏の夜だというのに、その冷たさは肌に刺さるようで、鳥肌が立つのを感じた。
「おい、なんか聞こえないか?」隣の友人が突然言った。
耳を澄ますと、波の音に混じって、微かにすすり泣くような音が聞こえてきた。
風の音ではない。
まるで誰かが苦しみながら泣いているような、そんな音だった。
「気のせいだろ…?いや、やめてくれよ」
僕たちは無理やり笑いながら、その異様な雰囲気を振り払おうとした。
しかし、灯籠はどんどんこちらに戻ってくる。
そしてそのすすり泣くような音は、確実に大きくなっていた。
「もう帰ろう、これはヤバいかもしれない」
僕たちがそう言いかけた瞬間、一番近くにいた友人のリョウが突然、何かに引き込まれるように海に足を取られた。
「おい、リョウ!」
慌てて手を伸ばしたが、彼の体はまるで見えない力に引っ張られているかのように、あっという間に海の中へと消えた。
波の音は静かで、まるで彼がそこにいたことさえも嘘のようだった。
「リョウ!戻ってこい!」ケンが必死に叫んだが、返事はなかった。
僕たちは動けなかった。何が起きたのかもわからず、ただ震えるばかりだった。
その瞬間、灯籠の一つが僕たちの足元に漂い着いた。
灯籠の中の炎は揺らぎながらも消えずに、まるで僕たちをじっと見つめているかのようだった。
すすり泣く音はまだ続いている。
まるでリョウが助けを求めているかのように、海の向こうから響いてくるようだった。
その夜、リョウは二度と姿を現さなかった。
警察が捜索したが、遺体は見つからなかった。
あの不気味な冷気とすすり泣きの音が僕たちの頭から離れず、いつまでも心に重くのしかかっている。
そして、毎年お盆の夜になると、僕たちは二度とその海に近づこうとはしなかった。
灯籠が戻ってくるたびに、リョウがどこかで泣き続けているのではないかという不安が、今でも消えないままでいる。







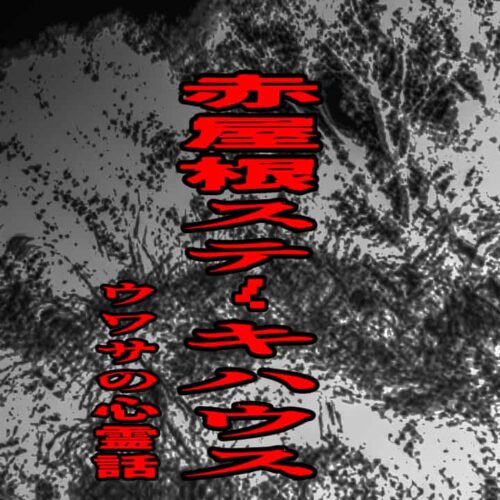

のウワサの心霊話-500x500.jpg)



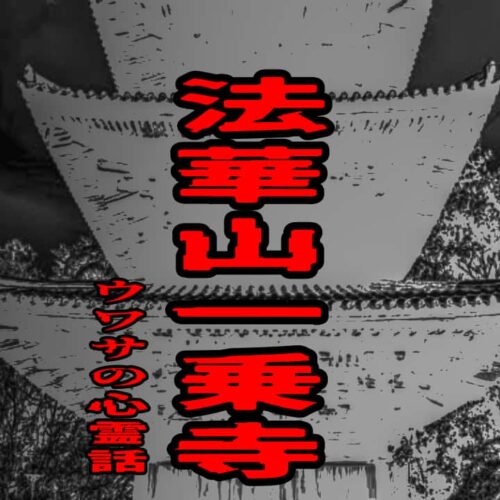
コメント