お盆の夜、風が少し冷たく感じられる夕暮れに、僕は庭で迎え火を焚いていた。
静かな庭先に炎が揺れ、オレンジ色の光が地面に複雑な影を落としている。
普段ならば賑やかに家族が集まる時期だが、今年は少し違った。
数日前に亡くなった祖母のことが、僕たち家族の心を重くしていた。
「おばあちゃん、無事に帰ってきてくれるかな…」そんなことをぼんやりと考えながら、炎を見つめていると、ふと気配を感じた。
振り返ると、祖母が庭の片隅でじっと火を見つめていた。
「おばあちゃん…?」
思わず声をかけた。彼女は確かに、ほんの数日前に亡くなったはずだ。
自分の目を疑いながらも、彼女の姿はあまりに自然で、まるで何事もなかったかのように立っている。
祖母は僕に目もくれず、炎の揺らぎをじっと見つめていた。
風が吹くたびに火が揺れる度、その目はさらに深く何かを探しているかのように鋭くなる。
彼女の顔には、どこか悲しみと決意が混じったような表情が浮かんでいた。
「おばあちゃん、どうして…?」僕は思わず近づこうとしたが、その一瞬、彼女が小さくつぶやくのが聞こえた。
「来てるよ…もう、帰らないといけないんだよ…」
その言葉は耳元でささやかれたように鮮明だったが、あまりにも冷たく、そして遠く感じられた。
僕は背筋に寒気が走るのを感じ、立ちすくんだ。
その瞬間、祖母の姿はふっと消えた。まるでそこに何もなかったかのように、
突然、影も残さずに。
風が再び吹き、迎え火の炎が一瞬揺れた。
僕はその場に立ち尽くし、何が起こったのか理解できずにいた。
「おばあちゃん…?」
周囲を見渡しても、祖母の姿はどこにもない。
ただ、風に揺れる炎だけが静かに燃え続けていた。
その場にいたのは僕だけではなかったのかもしれない。
翌朝、家族にこのことを話すと、皆信じられない様子だった。
特に母は「おばあちゃんはもう亡くなったのよ」と何度も繰り返し、僕を慰めようとした。
だが、あの夜、確かに僕の目の前に祖母はいた。
そして彼女は「帰らないといけない」と言ったのだ。
迎え火の影に潜む何かが、祖母を連れ去ったのだろうか。
彼女は何かに導かれるように消えていった。
それ以来、僕はお盆の迎え火を焚くたびに、あの時の光景が頭に蘇る。
祖母は本当に迎え火に呼ばれて帰ったのだろうか?
それとも、もっと深い闇の中へと消えていったのだろうか。








のウワサの心霊話-500x500.jpg)
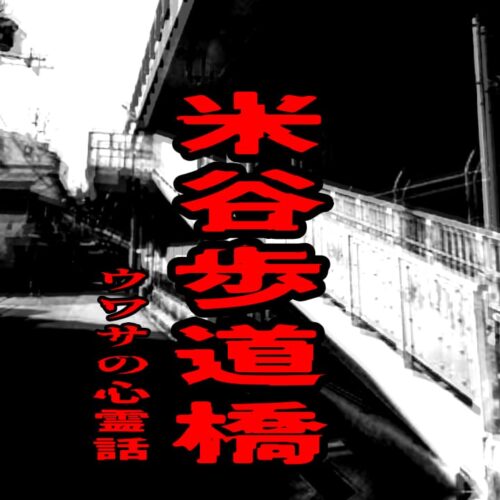
のウワサの心霊話-500x500.jpg)



コメント