広島県三次市に位置する比熊山には、「たたり石」と呼ばれる不気味な岩を中心に、老爺の霊の目撃や祟りによる怪異など、古くから数々の心霊現象が語り継がれている。今回は、比熊山にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
比熊山とは?

比熊山(ひぐまやま)は、広島県三次市三次町に位置する標高332メートルの山である。
戦国時代には毛利家の家臣であった三吉広高の居城がこの山頂に存在し、今では「千畳敷」と呼ばれる平坦な広場が広がっている。
この山を語るうえで欠かせない存在が「たたり石」である。
正式には「神籠石(こうごいし)」と呼ばれ、神が宿る神聖な石とされてきたが、一方で「触れると祟りが起こる」とも伝えられ、畏怖の対象ともなっている。
現在でもその異様な存在感は、訪れる者の背筋を凍らせる。
この石が特に有名になったのは、江戸時代に書かれた『稲生物怪録(いのうもののけろく)』によるものである。
この物語には、実際にこの石に関わった少年が、30日間にわたって怪異に襲われ続けたという、信じがたい恐怖が描かれている。
比熊山の心霊現象
比熊山の心霊現象は、
- 老爺の霊が現れる
- 祟りにあう
である。以下、これらの怪異について記述する。
老爺の霊が現れる
比熊山の登山道を夜に訪れた者の中には、「ボロボロの衣をまとった白髪の男を見た」という証言が後を絶たない。
その霊は決してこちらを向かず、山頂のたたり石に向かってよろよろと歩いているという。
その姿は一瞬で視界から消えることもあり、姿を見かけた者の中には体調を崩したり、不運が立て続けに起きるといった報告もある。
老爺の霊は一体何者なのか。彼が「たたり石」に導かれるように歩く様子から、「祟りの媒介者」ではないかという噂もある。
祟りにあう
たたり石に不用意に触れたり、ふざけ半分で写真を撮った者には、得体の知れない不幸が降りかかるという。
怪我や病気、失職、家族の死——。
実際、地元の住民の間でも「たたり石には絶対に手を触れるな」と代々言い伝えられている。
江戸時代の『稲生物怪録』では、主人公が木札をこの石に結びつけたことで、夜な夜な妖怪が現れ、宙に浮かされる、巨大な目玉に睨まれる、異形の存在に襲われるなど、30日に渡って身の毛もよだつ怪異が続いた。
現代においても、肝試し目的で訪れた若者が帰宅後に体調を崩し、精神的に錯乱したまま行方不明となった事例もあるという。
自殺の名所ともささやかれ、山中で発見された変死体がニュースにはならず、静かに処理されたという噂もある。
比熊山の心霊体験談
ある女性は、友人と夜の比熊山を訪れた際、山頂付近で「誰かの視線を感じる」と口にした。
その直後、彼女は突然しゃがみ込み、「おじいさんが、こっちを見てる……」と震え出したという。
友人が周囲を確認しても誰の姿もなかったが、帰宅後、女性の足には無数の引っかき傷のような痕が残っていた。
また、別の登山者は昼間に山を訪れた際、「たたり石」の写真を撮ろうとしたところ、カメラが何度もフリーズし、最後には液晶画面に「かえれ」という文字が浮かび上がったという。
機器の不調としては説明がつかず、撮影後に彼は高熱を出し、しばらく意識不明となった。
比熊山の心霊考察
比熊山の心霊現象は、古くからの伝承と密接に結びついている。
江戸時代に記録された『稲生物怪録』は創作と片付けるにはあまりにも具体的かつ詳細であり、当時の人々が実際に体験した超常現象を元にしている可能性が高い。
また、たたり石が存在する「千畳敷」は、戦国時代の居城跡であり、合戦や処刑が行われた可能性もある。
土地に染みついた怨念が霊的な磁場を形成し、時を越えて怪異を引き寄せているのかもしれない。
老爺の霊は、戦国時代の落武者、あるいは祟りによって命を落とした者の成れの果てとも考えられる。
比熊山における怪異は、好奇心や軽い気持ちで立ち入るにはあまりにも危険すぎる領域であると言える。
心霊スポットとしての知名度はまだ高くはないが、それゆえに語られていない“闇”が深く息づいている。
決して、軽い気持ちで足を踏み入れてはならない場所である。



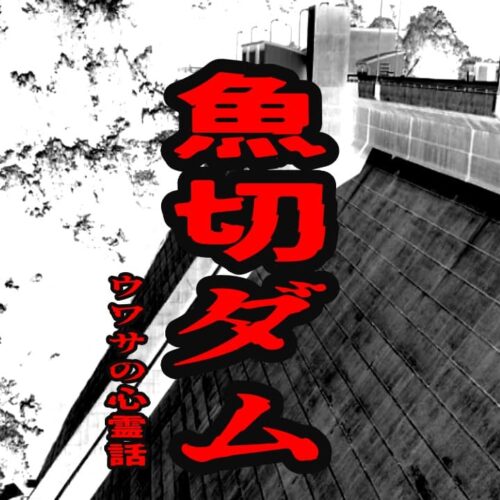


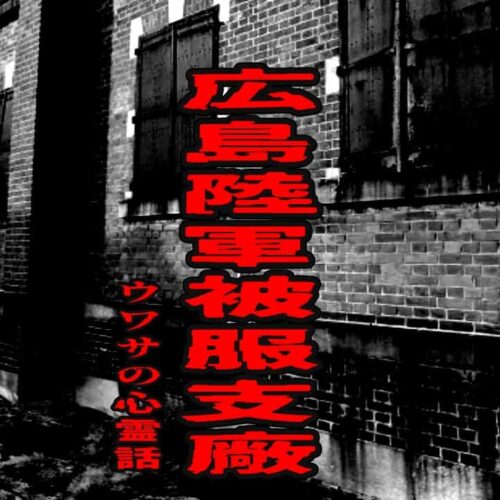
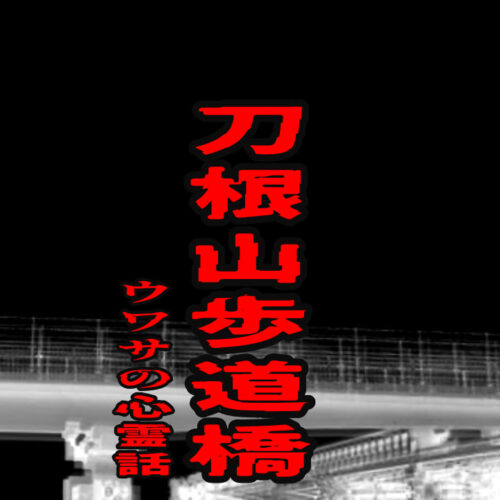


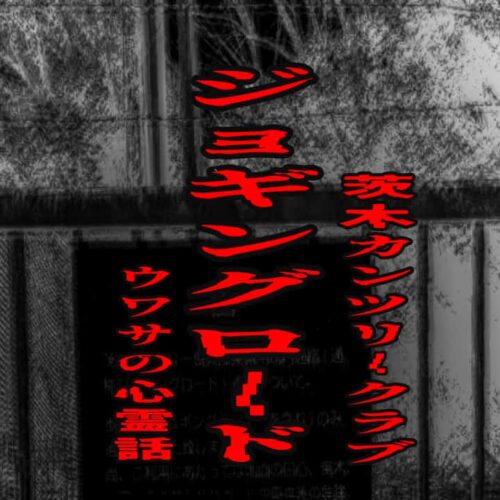
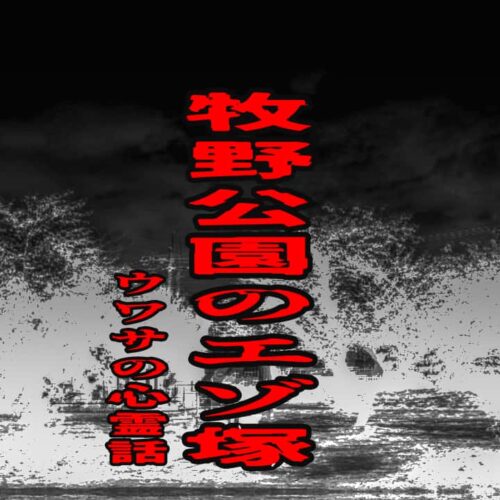
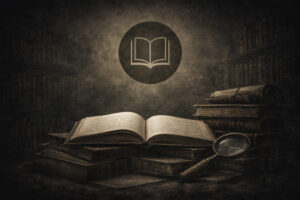
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
コメント