高知市升形に建つ「吉野朝廷時代古戦場址の碑」には、南北朝の血で染まった土地ゆえの不気味なウワサが囁かれている。今回は、その吉野朝廷時代古戦場址の碑にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
吉野朝廷時代古戦場址の碑とは?

高知市升形の国道55号線沿い、出雲大社土佐分祠の参道にひっそりと佇むこの碑は、南北朝時代(1333〜1392)における土佐最大の激戦地を示すものである。
当時、土佐は足利尊氏の重臣・細川氏が支配し、北朝方の勢力が強かった。
しかし、大高坂松王丸が南朝方として立ち上がり、大高坂城(現・高知城)を本拠に激戦を繰り広げた。
南朝方には、後醍醐天皇の皇子・花園宮満良親王をはじめ、新田綿打入道や金沢左近将監らの武将が加わり、潮江山(筆山)に陣を構えて奮戦したという。
北朝方は安楽寺(現在の升形近辺にあったとされる)に砦を築き、激しい攻撃を繰り返した。
戦いは興国元年(1340)に終結し、大高坂城はついに陥落。松王丸は城の西木戸付近で壮絶な最期を遂げ、花園宮は西国へ逃れたと伝えられている。
今ではただ静かに碑が残るのみだが、夜になるとこの地には、かつての戦乱を今も引きずる怨念が漂うと語られている。
吉野朝廷時代古戦場址の碑の心霊現象
吉野朝廷時代古戦場址の碑の心霊現象は、
- 夜中になると落武者の霊が出る
- 微かな声や白い影を見た
である。以下に詳しく述べる。
この場所にまつわる心霊現象として最も有名なのが、「夜中になると落武者の霊が出る」という話である。
深夜、出雲大社の参道や碑の前に、鎧をまとった武士の影が立つのを見たという人が昔からいたという。
それは松王丸の家臣、あるいは討ち死にした武者の霊とされ、戦の無念を今もこの地に留めているのだと伝えられている。
しかし近年、この落武者の霊を“実際に見た”という体験談は極めて少ない。
霊感の強い者が「何かの気配を感じた」「空気が急に重くなった」と語ることはあるが、明確な姿を見たという報告はほとんどない。
おそらく、その存在を感じ取れるのは、特殊な感受性を持つごく一部の人だけなのだろう。
多くの人にとっては、碑の前を通っても何の異常も感じることはない。
それでも夜の静寂に包まれたこの場所に立つと、なぜか背筋が粟立つような感覚に襲われる。
それは風の音や木の擦れる音では説明のつかない、どこか遠い時代の息づかいのようでもある。
かつて無数の命が散った戦場の空気は、七百年の歳月を経ても完全には消えていないのかもしれない。
なお、ほかの心霊現象――たとえば白い影が写る、声が聞こえるといった報告もあるが、いずれも体験談はごく少なく、信憑性に乏しい。
それらは伝承の名残として人々の口に上る程度であり、現在では確認できるものではない。
吉野朝廷時代古戦場址の碑の心霊体験談
ある人物が夏の夜に碑の前を通りかかった際、どこからともなく“甲冑のきしむ音”を聞いたという。
振り返っても誰もおらず、足音すらなかったというが、「もしかすると戦の者たちがまだここにいるのだろう」と語っていた。
そのほかにも、夜にここを訪れた若者が「視線を感じる」と話しており、そうした“気配”だけは今も途絶えていないのかもしれない。
吉野朝廷時代古戦場址の碑の心霊考察
「落武者の霊が出る」という話は、戦場としての凄惨な歴史を背景に生まれた土地の記憶そのものである。
血と鉄、そして無念の思いがこの地の空気に刻まれ、敏感な者にだけ届くのだろう。
実際の姿を目にする者が少ないのは、怨霊が弱まったからではなく、現代の人々が“感じる力”を失ったからかもしれない。
昼は穏やかな史跡であっても、夜には七百年前の気配が微かに蘇る。
その風に耳を澄ませた時、あなたの背後を通り過ぎるのは――もしかすると、戦に散った落武者の影なのかもしれない。
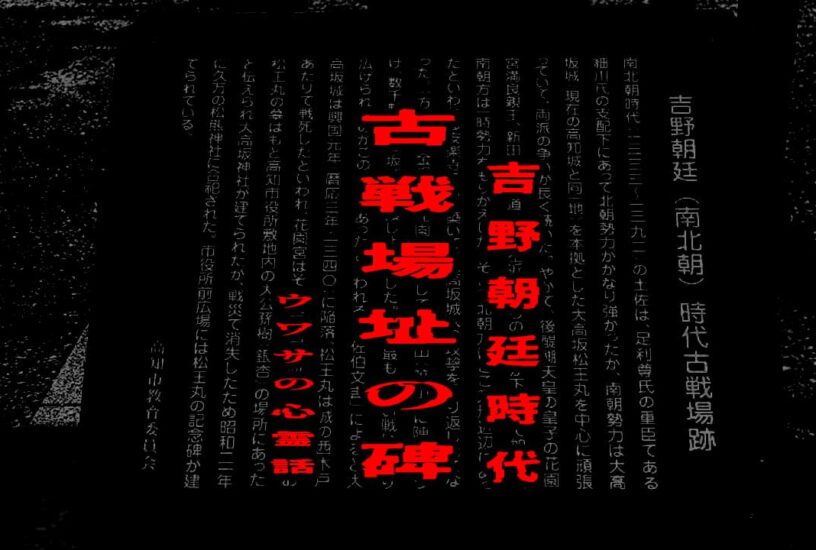

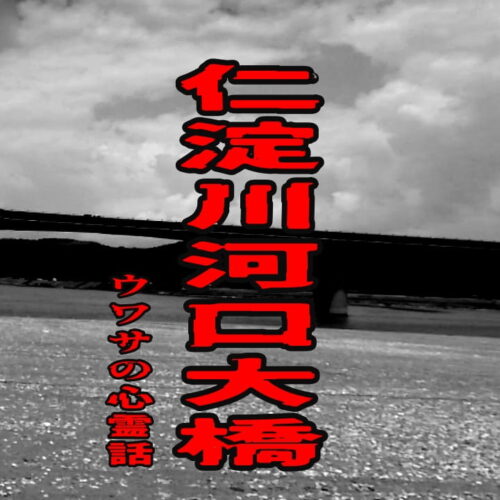
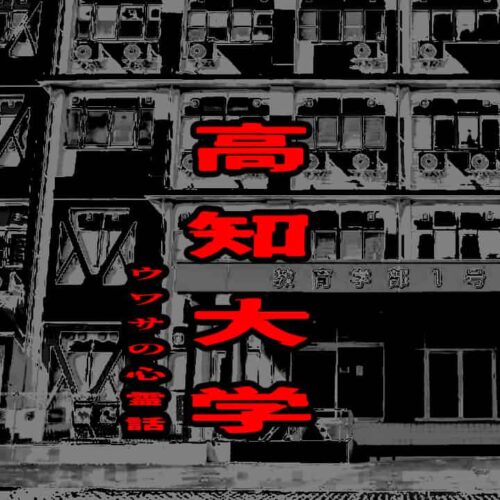
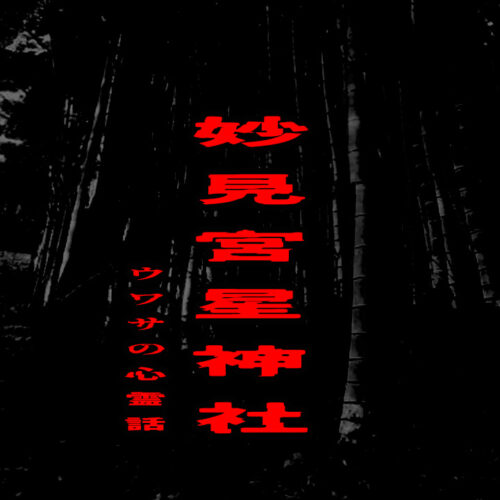
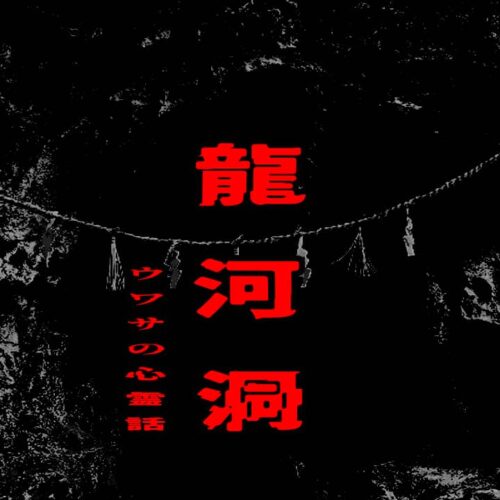
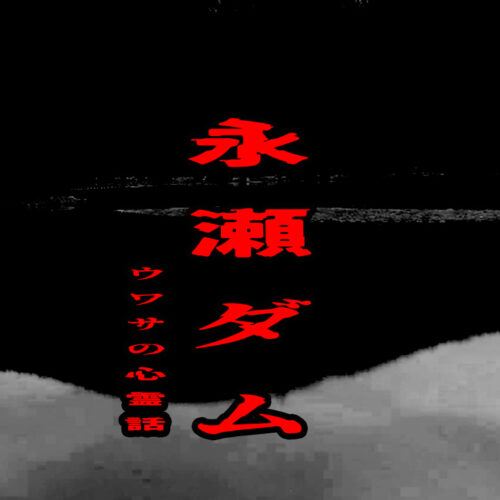
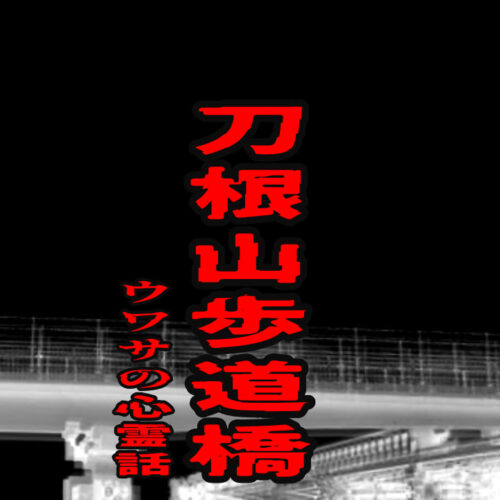


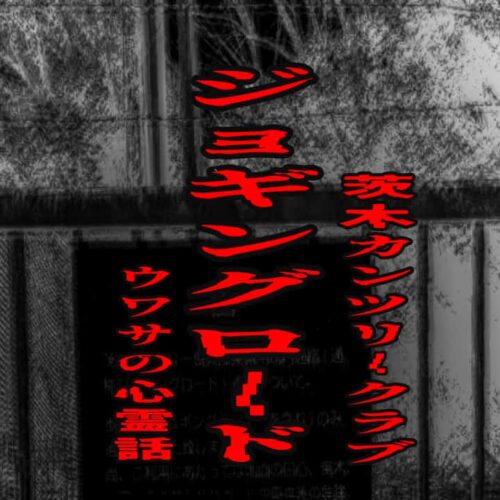
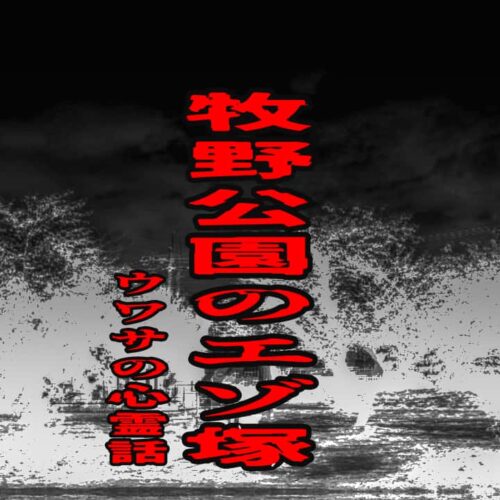
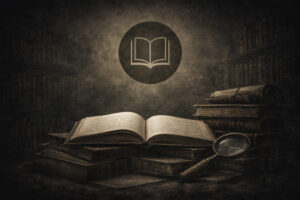
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
コメント