高知市に鎮座する高知縣護國神社には、戦没者の御霊を祀る厳かな空気が漂っている。そんな神聖な場所でありながら、夜になると「足音が聞こえる」という不思議なウワサが囁かれている。今回は、高知縣護國神社にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
高知縣護國神社とは?

高知縣護國神社(こうちけんごこくじんじゃ)は、高知県高知市にある神社である。
明治元年(1868年)、土佐藩主・山内豊範が、戊辰戦争の東征に従軍して戦死した藩士105柱を慰霊するため、五台山大島岬の地に創建したことに始まる。
のちに明治維新の志士たち、武市半平太命・坂本龍馬命・中岡慎太郎命・吉村寅太郎命をはじめ、堺事件(慶応4年)で命を落とした土佐藩士11名、さらに日清・日露・太平洋戦争に至るまで、国難に殉じた高知県ゆかりの戦没者4万1千余柱が祀られている。
昭和14年(1939年)に「高知縣護國神社」と改称され、現在に至るまで、英霊の眠る場所として県内有数の慰霊の地となっている。
高知縣護國神社の心霊現象
高知縣護國神社の心霊現象は、
- 境内を歩くと、誰もいないはずなのに「足音」が後ろから聞こえる
- 夜、鳥居の向こうから視線を感じる
- 写真を撮ると、人影のようなものが写り込む
- 霊感のある者だけが、境内に「人ならぬ気配」を感じ取る
である。以下、これらの怪異について記述する。
高知縣護國神社の心霊現象の中でも最も知られているのが、「謎の足音」である。
夜更け、参道を一人歩いていると、石畳の上で「コツ…コツ…」と靴音のような音が後ろからついてくるという。
振り返っても、そこには誰もいない。
足音は止まることもあれば、まるで距離を取るように遠ざかることもある。
この音は、戦没者たちの行進の名残ではないかと語る者もいる。
誰かを脅かすためではなく、今もなおこの地を守り続けているのかもしれない。
また、境内の奥や社殿周辺では、「何かに見られている」ような感覚を覚える人がいるという。
昼間の清らかな空気の中では何も感じないが、夕暮れを過ぎると、空気が重たく沈み込み、誰もいないはずの空間から静かな気配が漂うという。
さらに、参拝時に撮影した写真に、ぼんやりと人影のようなものが写るという報告もある。
形は明確でなく、白い靄のように見えることが多い。
中には、帽子をかぶった兵士の姿に見えるという証言もある。
高知縣護國神社の心霊体験談
ある地元の男性は、深夜に仕事帰りで境内を通り抜けた際、はっきりと後ろから足音を聞いたという。
夜の神社は外灯も少なく、風の音以外は何も聞こえない。
にもかかわらず、「砂利を踏む音」が自分の歩調に合わせるように鳴り続けたという。
怖くなって足を止めると、音も止まる。
再び歩き出すと、また「コツ、コツ」と音が響いた。
振り向いても誰もいない。
社殿の方を見ると、灯篭の明かりが揺れ、その瞬間だけ妙に空気が冷たく感じられたという。
彼は「失礼なことをしてはいけない」と手を合わせ、静かにその場を離れた。
それ以来、夜の境内には近づかないようにしているという。
高知縣護國神社の心霊考察
高知縣護國神社で語られる現象の多くは、「恐怖」というよりも「静けさの中に宿る存在感」である。
戦没者を祀るこの場所では、確かに多くの魂が安らかに眠っている。
その霊たちは決して悪意をもって現れるのではなく、今もなおこの地を見守っているのかもしれない。
霊感のある者だけがその気配を感じ取るのは、敬意をもって参拝する者への応答ともいえるだろう。
高知縣護國神社は、恐ろしい場所ではなく、“静かな畏れ”をもって接するべき聖域である。
夜に足音を聞く者がいるのならば、それは恐怖ではなく、英霊たちの歩みが今も続いているという証なのかもしれない。
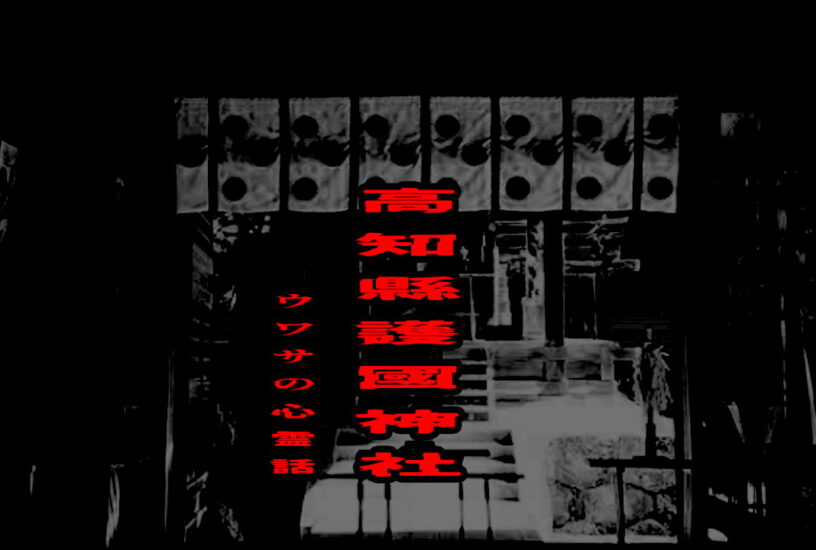
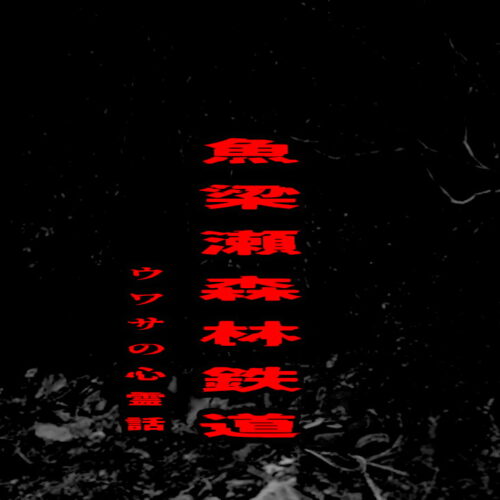
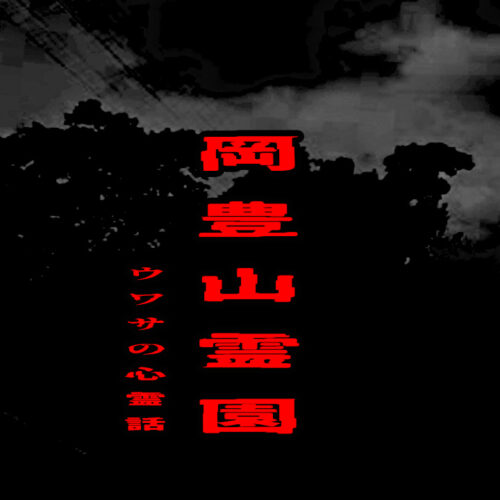
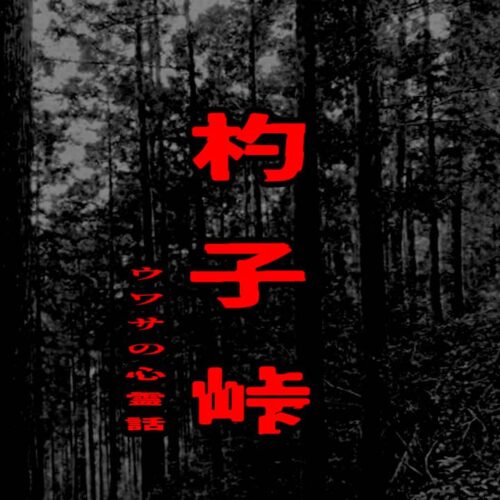

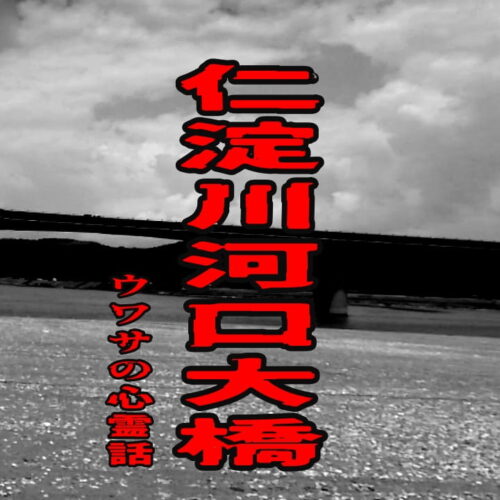
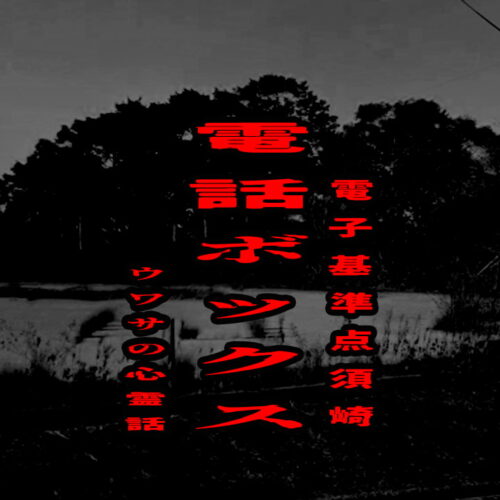
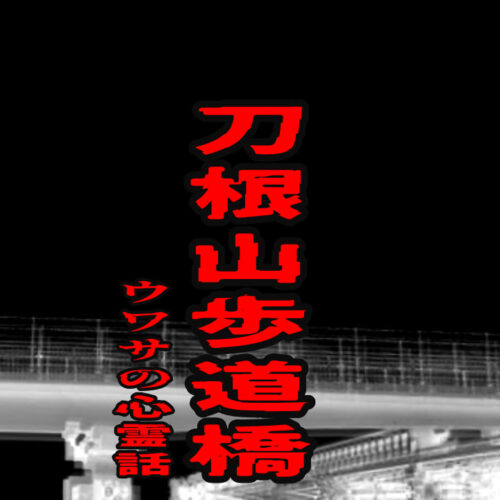


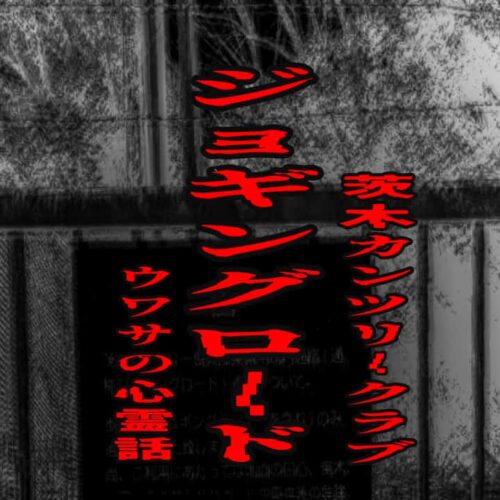
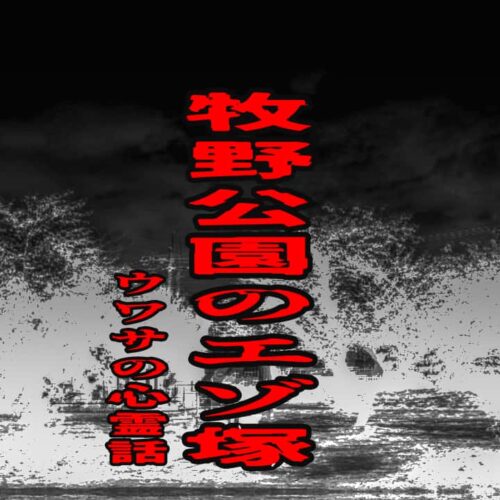
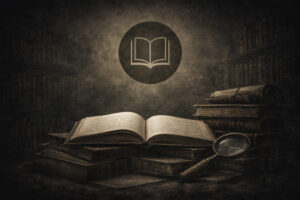
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
コメント