夏の終わり、お盆の季節がやってきた。
毎年この時期には、祖母の家で送り火を焚くのが我が家の習慣だった。
先祖たちを見送り、再びあの世へと帰ってもらうための儀式だ。
火を灯し、その炎を見つめながら静かに祈る時間は、いつも厳かで心が落ち着くものだった。
その年も、祖母は庭に小さな焚火を準備していた。
赤々と燃える炎が、闇夜の中で踊っているかのように揺れていた。
家族全員で手を合わせ、祖父や他の先祖たちを見送る時がやってきた。
炎が高く燃え上がり、暖かな光が周囲を包んでいる中、突然冷たい風が吹き始めた。
今まで穏やかだった夜の空気が一変し、強い風が庭中を駆け抜ける。
焚火の炎が激しく揺れ、まるで何かがその中で蠢いているかのようだった。
ふと、炎の中に何かが見えた。
よく見ると、そこには人影があった。
最初は幻だと思ったが、その影は次第に明確になり、まるで火の中から立ち上がるようにして現れたのだ。
燃えさかる炎の中から、その人影がゆっくりとこちらに向かってくるような気配がした。
「何だ、あれは…?」
不安に駆られた瞬間、祖母が突然大きな声で叫んだ。
「戻っちゃいけない!」
その声は、これまで聞いたことのないような鋭いもので、俺はその場に凍りついた。
祖母は素早く焚火に駆け寄り、火を激しく蹴散らした。
炎が一瞬にして吹き飛び、辺りは暗闇に包まれた。
風もピタリと止まり、異様な静けさが戻ってきた。
「おばあちゃん、今のは…?」
息を整えながら、祖母に尋ねたが、彼女は無言のまま、こちらを一度も見ようとしなかった。
その表情は険しく、何かを知っているようだったが、それを語ろうとはしなかった。
家族全員がただ黙って、祖母の行動に戸惑っていた。
それ以来、祖母はその出来事について一度も話すことはなかった。
何が見えたのか、なぜあんなに必死だったのか、誰も尋ねることができなかった。
家族はあの夜のことを忘れようとしたが、俺の頭の中には今でもあの炎の中に立ち上がる影が鮮明に焼き付いている。
あれは、いったい誰だったのだろうか。
そして、なぜ祖母は「戻っちゃいけない」と言ったのだろうか。
送り火の儀式は、あの年を境に祖母の家では行われなくなった。







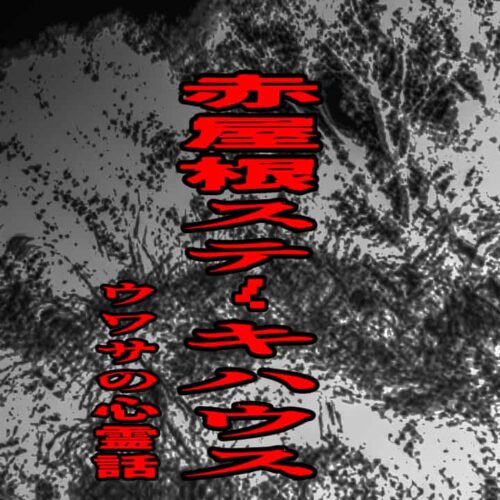

のウワサの心霊話-500x500.jpg)



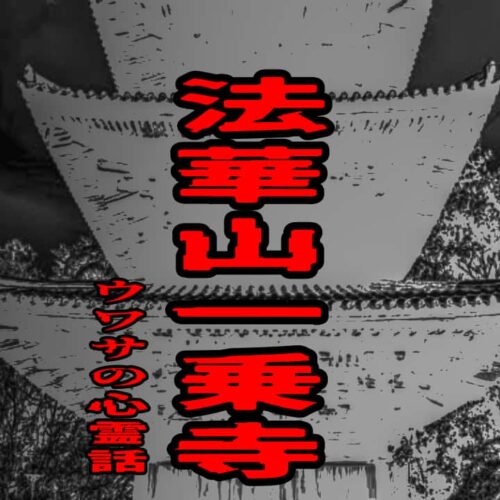
コメント