山口県小月に位置する茶屋池には、かつてこの地に存在した遊郭にまつわる数々の悲劇が残されており、今なおその名残が“見えない形”で漂っているという。今回は、茶屋池にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
茶屋池とは?

茶屋池は、山口県下関市小月の高台にひっそりとたたずむ大きな池である。
近くには地蔵尊が二体祀られている小さなお堂があり、そのそばには一本の古い墓が立っている。
この墓は、江戸時代に実在した女性「槙野ヒサ」のものとされ、彼女の人生と共に、この池にまつわる血と涙の歴史が静かに語り継がれている。
時は清末藩の三代藩主・政苗、四代・匡邦公の治世。藩財政の立て直しを狙い、小月の地に遊郭が設けられた。
そこでは、人買いによって連れて来られた娘や、騙されて売られた女性たちが無残にも生きる希望を失い、数々の悲劇が繰り返されたという。
茶屋池の心霊現象
茶屋池の心霊現象は、
- 夜になると池の水面から複数の女のすすり泣く声が聞こえてくる
- 女の霊が池の周囲に立ち尽くしているのが目撃される
- 池に近づくと突然体が重くなり、足を引っ張られるような感覚に襲われる
- 池のほとりに立つお堂で、誰もいないのに線香の匂いが漂ってくる
である。これらの現象は、まるで過去の悲劇を繰り返し訴えるかのように、訪れる者の心を静かに、しかし確実に締めつけるのである。
以下、これらの怪異について記述する。
茶屋池ではかつて、借金に苦しむ女郎七人が、お互いの身体を綱で結び合い、池に飛び込んで集団投身自殺を遂げたという凄絶な逸話が残されている。
綱で縛り合うという行為は、互いに逃げ場をなくし、絶望を共有することでしか語れない悲壮な覚悟の表れである。
この事件の背景には、遊郭という制度の中で搾取され、生きる選択肢を奪われた女性たちの痛ましい現実があった。
池の底には、いまだ彼女たちの怨念が沈んでいるのではないかと囁かれている。
また、かつて遊郭に騙されて連れて来られ、身を投げようとした一人の女性「槙野ヒサ」は、天寧和尚という僧によって救われた。
しかし、その後、和尚は藩の政策に異を唱えたことで流罪となり、六連島に流された。
ヒサは和尚の放免を求めて十年に渡り奔走するが、叶わず、和尚は流刑地でその生涯を終えた。
ヒサは和尚の死を悼み、茶屋池の堤にお堂を建てて、自殺者の供養と救済を生涯続けたとされる。
彼女の墓前には今も線香と花が絶えることがないというが、それが「誰か」が供えているのか、「何か」に供えさせられているのか――それは誰にもわからない。
茶屋池の心霊体験談
地元の住民によれば、池の近くを夜に通ると、水辺から目をそらせない“視線”を感じるという。
ある男性は、池のそばを通っている最中、車のミラー越しに白い着物の女性が立っているのを見たが、振り返ってもそこには誰もいなかったという。
また、茶屋池のほとりに立つお堂の前では、誰もいないはずなのに、「誰かに見られている」「誰かが立っている」ような強い気配を感じて、足早に立ち去る人も少なくない。
池の水は透明で美しいが、決して覗き込んではならない。
そこには、今もなお“底”から誰かが手を伸ばしているという噂が絶えないからである。
茶屋池の心霊考察
茶屋池の心霊現象は、決して単なる“古い噂”で片づけられるものではない。
その背景には、制度としての遊郭、女性たちの犠牲、そして命をもって抗った者たちの記憶が染みついている。
特に、女郎たちが綱で結び合って入水したというエピソードは、単なる自殺ではなく、抗議や抵抗としての“集合死”であり、その念は強く、深い。
自らの意志で命を絶ったというよりも、生かされる術がなかった者たちの“呪い”に近い。
また、槙野ヒサという一人の女性が、たった一つの救いであった和尚を守れなかった無念を抱きながら生涯を終えたという話は、霊的に非常に強い意味を持つ。
彼女の祈りと供養の想いは確かに池に刻まれているが、それだけでは癒せないほど、深く濁った感情がこの池には沈殿しているのだろう。
茶屋池――その美しさの裏には、沈められた魂たちの声なき声が今もなお木霊している。


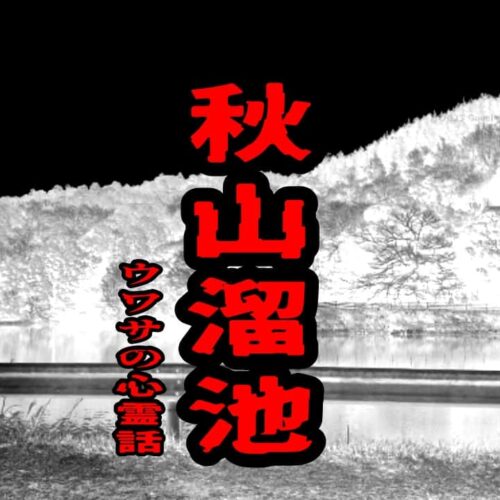
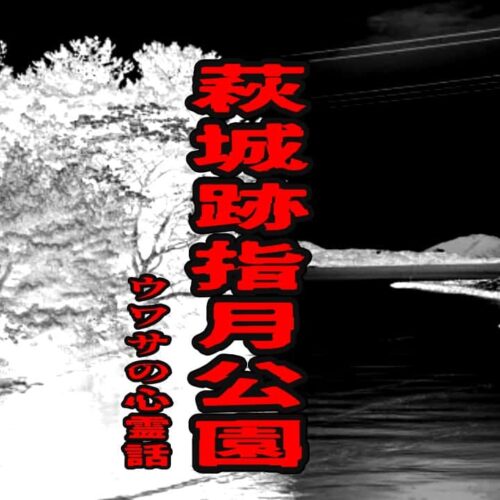
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
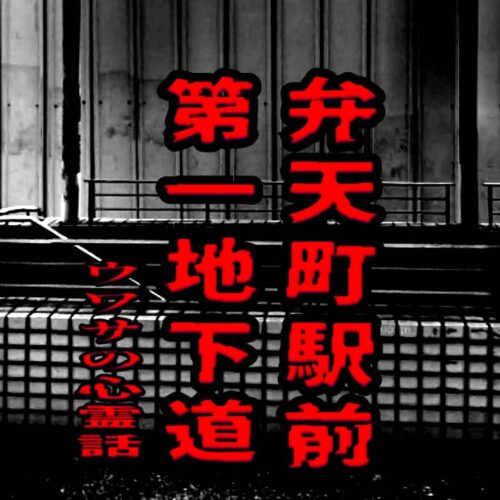
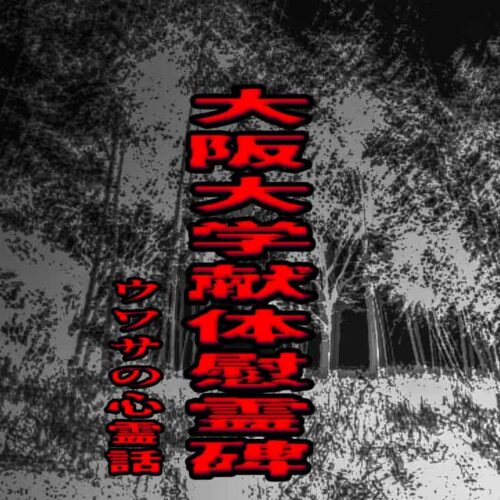
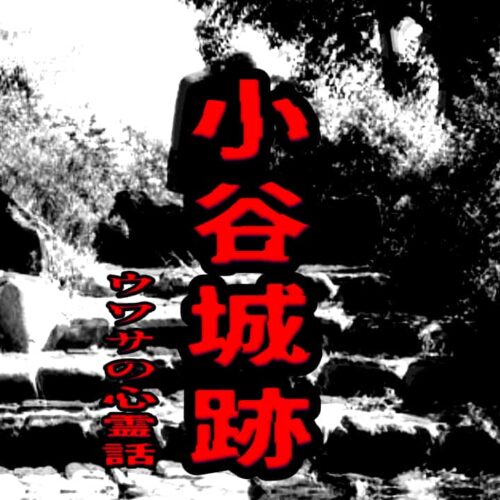
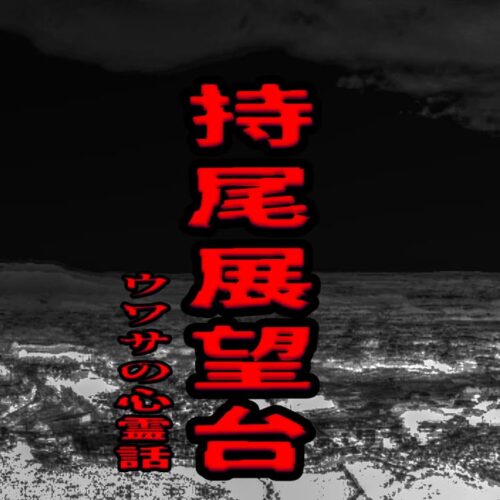
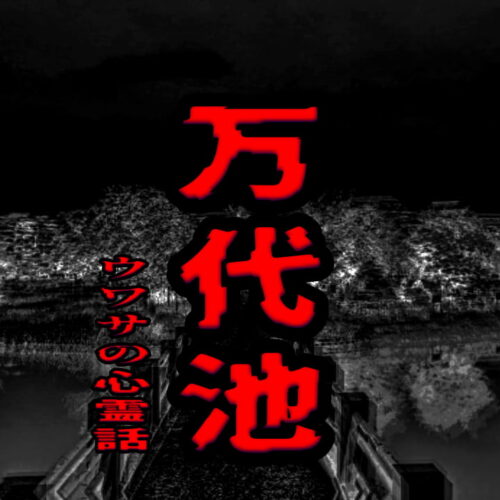
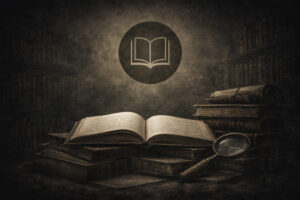
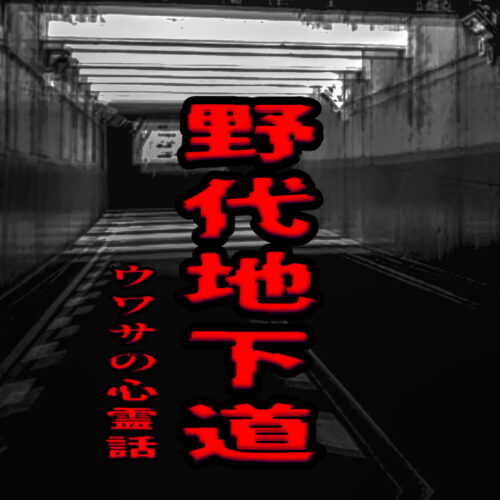
コメント