徳島市国府町に佇む「夜泣き地蔵」は、夜ごとに赤ん坊の泣き声が聞こえるという怪異で知られている。池の底から響いたという泣き声と、そこから発見された地蔵にまつわる不気味な伝承は今も語り継がれており、子宝信仰と結びついた独特の心霊話として恐れられている。今回は、夜泣き地蔵にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
夜泣き地蔵とは?

徳島市国府町和田居内の鮎喰川の土手を下ると、立派なお堂に祀られた地蔵が現れる。
建立は安政6年(1859年)とされ、三段の板状台石の上に蓮台と地蔵座像が据えられ、全高は3.23メートルに及ぶ堂々たる姿である。
堂内には、拳ほどの小さな地蔵が数え切れぬほど並べられている。
それぞれに赤いよだれかけが施され、一体ずつがまるで「子ども」のような姿をしている。
この「小さな地蔵」をめぐり、古くから奇妙な言い伝えが残されているのである。
夜泣き地蔵の心霊現象
夜泣き地蔵の心霊現象は、
- 夜ごと赤ん坊の泣き声が響き渡る
- 泣き声が池の水底から聞こえてくる
- 池をさらうと地蔵が現れた
- 小さな地蔵を抱いて眠ると夜泣きが聞こえ、不思議と子を授かる
である。以下、これらの怪異について記述する。
かつてこの地で、毎晩のように赤ん坊の泣き声が響いたという。
辺りを探しても誰もいない。だが泣き声は確かに聞こえ、それを辿ると池の方角から漏れ出していた。
まるで水の底から、幼子が必死に泣き叫んでいるかのように。
翌日、人々が池をさらうと、泥の中から一体の地蔵が現れた。
不憫に思った村人たちはお堂を建て、丁重に祀ったという。
その晩を境に、泣き声はぴたりと止んだ。以来、この地蔵は「夜泣き地蔵」と呼ばれるようになったのである。
さらに、この地蔵には奇妙な信仰が生まれた。子宝に恵まれぬ者が小さな地蔵を持ち帰り、抱いて眠ると赤子の泣き声が耳元に響き、やがて子を授かるといわれている。
そして願いが叶うと、持ち帰った小地蔵に加え、新たにもう一体を返す習わしが生まれた。
そのため現在でも堂内には無数の小地蔵が積み重なるように置かれている。
夜泣きが止まったはずの地で、今もなお「子を求める声」が響き続けているのかもしれない。
夜泣き地蔵の心霊体験談
ある参拝者は、堂内の小地蔵を抱いて一夜を過ごしたところ、真夜中に耳元でかすかな赤ん坊の泣き声を聞いたという。
その声は次第に大きくなり、布団の中で確かに「赤子が動く重み」を感じたと語る。
恐怖のあまり目を閉じ続けて朝を迎えると、腕に抱いていたはずの小地蔵は静かに元の場所に戻されていたという。
夜泣き地蔵の心霊考察
夜泣き地蔵の伝承は、洪水で命を落とした子供や、親に抱かれることなく逝った幼子の魂と結びつけられることが多い。
池の底から聞こえる泣き声は、その未練を象徴しているとも解釈できる。
一方で、子宝信仰と結びついた点は、恐怖と救済が表裏一体であることを示している。
赤ん坊の泣き声は「呪い」であると同時に「授かりもの」の兆しともされ、信仰する者にとっては畏怖と希望を同時に与える存在である。
つまり、夜泣き地蔵はただの供養ではなく、恐ろしい泣き声を背景に、命の循環そのものを映し出す異形の存在といえるだろう。


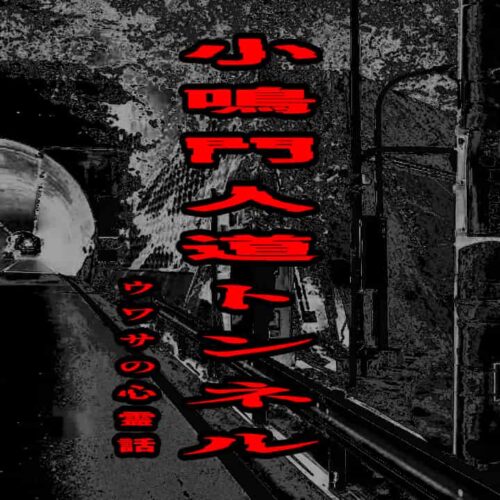
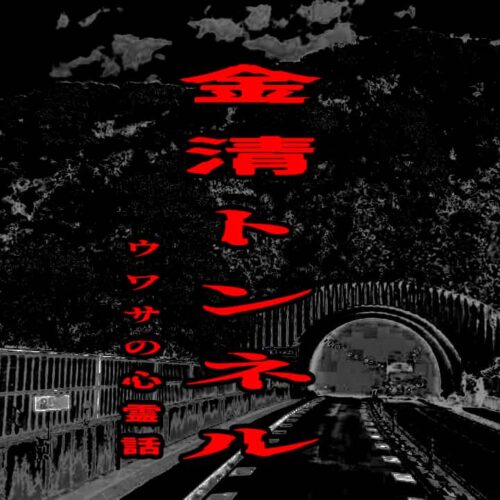
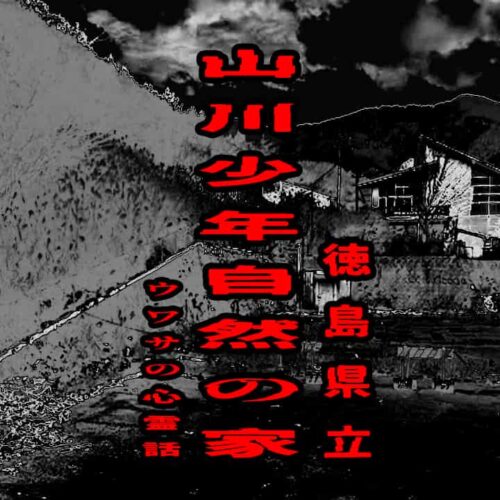


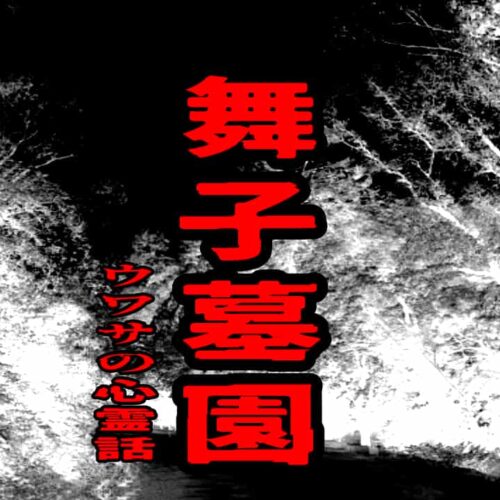
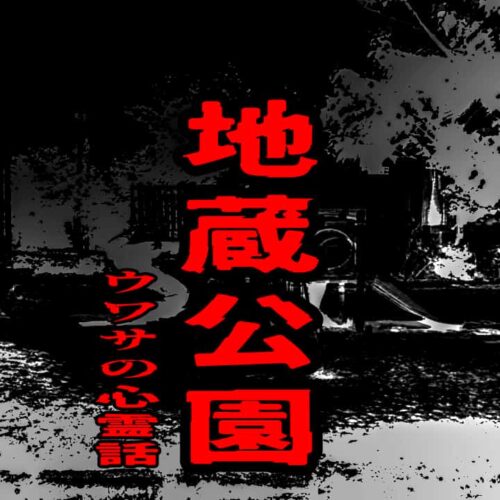
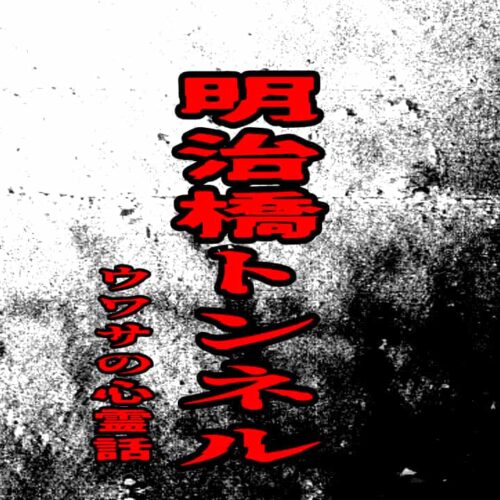
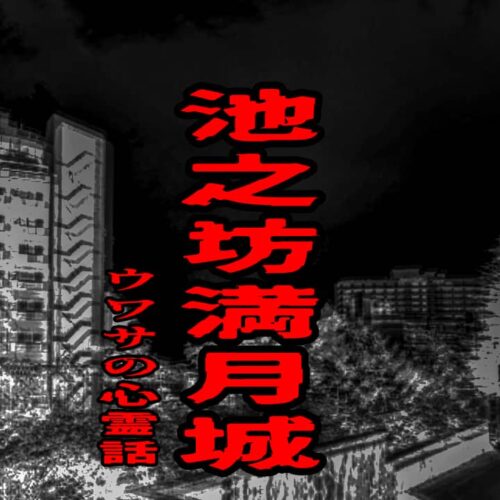
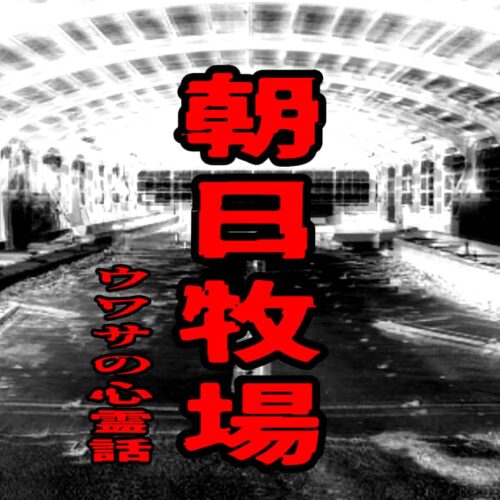
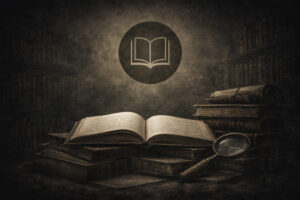
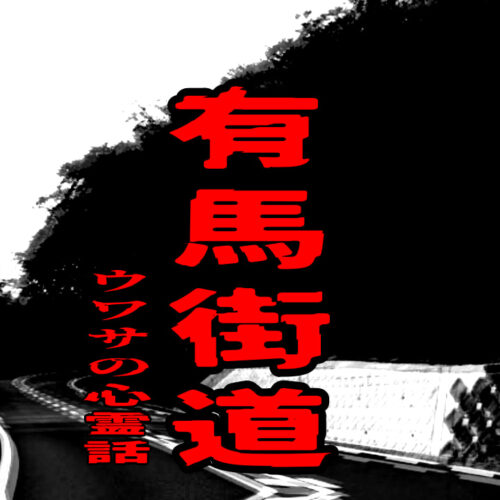
コメント