徳島県鳴門市に残る撫養城跡。現在は公園として整備されているが、この地には不可解な現象や異形の存在を目撃したという数多くの証言が残されている。昼夜を問わず現れる白装束の集団、首のない武士の妖怪「しゃらんこ」、そして崖の向こうへ消えた霊――。今回は、撫養城にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
撫養城とは?
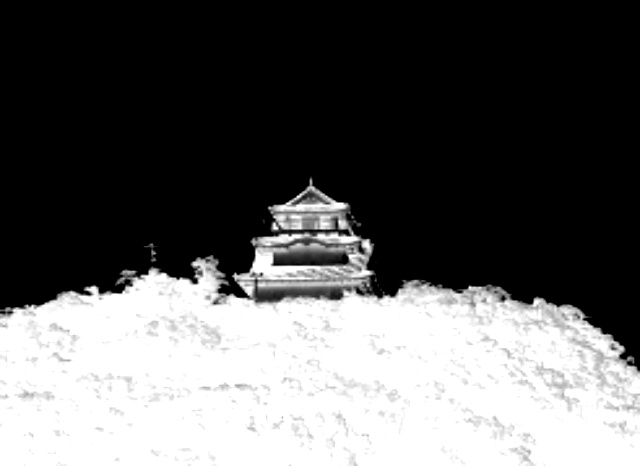
撫養城(むやじょう)は、徳島県鳴門市撫養町林崎に位置する山城跡であり、別名「岡崎城」や「林崎城」とも呼ばれている。
現在では「岡崎城跡」として市の指定史跡となっている。
築城時期や初期の城主については不明であるが、古くは小笠原氏の居城と伝わる。
その後、三好氏の配下である四宮氏が城主を務めたが、天正10年(1582年)には長宗我部元親が阿波国へ侵攻し、配下の真下飛騨守がこの城を守備する。
さらに天正13年(1585年)、豊臣秀吉による四国征伐後には蜂須賀家政が阿波国の領主となり、撫養城には益田正忠が城番として置かれた。
しかし、江戸幕府による「一国一城令」により、寛永15年(1638年)に廃城となった。
現在、城跡のある妙見山は「妙見山公園」として整備されており、三層の模擬天守が建てられているが、これは後年の建造物であり、実際の撫養城に天守は存在していなかった。
撫養城の心霊現象
撫養城の心霊現象は、
- 白い服を着た集団の霊が現れる
- 馬に乗った首のない武士の妖怪「しゃらんこ」の出現
- 崖へと向かい消え去る霊的存在
- 夜中に響く鈴の音
である。以下、これらの怪異について記述する。
撫養城跡を訪れた者の中には、奇怪な光景を目にしたという者が後を絶たない。
最も知られているのは「白い服を着た集団」の霊である。
昼間、子どもたちが遊びに訪れた際、かくれんぼをしていた最中に白装束の集団とすれ違ったという。
その集団はまるで儀式のように無言で列をなし、ゆっくりと山の斜面を歩いていた。
気になった子どもが後をつけると、彼らはやがて崖の方へと歩を進め、そのまま音もなく消えていったという。
崖の下を確認しても、そこには何の痕跡も残されていなかった。
現代の目で見ても、説明のつかない存在である。
また、撫養城跡では「しゃらんこ」と呼ばれる妖怪の目撃談も語り継がれている。
「しゃらんこ」とは、馬に乗った首のない武士の霊であり、馬の首元には鈴が括り付けられている。
深夜になると、どこからともなく鈴の音が「シャラン…シャラン…」と耳元に響き渡り、それが次第に近づいてくるという。
姿を見た者によれば、馬に乗った首のない武士が、まるで未だ任務を果たすかのように城の周囲を徘徊していたとのことである。
この城跡に現れる霊たちは、戦国時代の怨念や無念を超えた、もっと別種の“何か”であるという印象を与える。
定番の武士の霊というよりは、どこか宗教的な意味合いや儀式性すら感じさせる、不気味な存在である。
撫養城の心霊体験談
以下は、ある小学生が実際に体験したという出来事である。
それは夏の昼下がり、友人たちと妙見山へ遊びに行ったときのこと。
肝試しではなく、ただ純粋に自然の中で遊ぶ目的であったという。
かくれんぼを始め、隠れる場所を探して山中を歩いていた時、ふと、木々の向こうに白装束を着た集団の後ろ姿が見えた。
奇妙に思いながらも、何かのイベントかと考えた子どもは、その集団の後ろを少し距離を保ってつけていった。
しかし、集団が向かった先は崖であり、彼らはそこに到達した瞬間、煙のように霧散したという。
崖下を覗いても、何も見えなかった。
風もなく、音もなく、ただ“何か”がそこから消えたという事実だけが残った。
この体験を境に、妙見山は“昼間でも出る”場所として子どもたちの間で囁かれるようになった。
撫養城の心霊考察
撫養城に現れる霊たちは、戦国武将や落武者といった典型的な「城跡の幽霊」とは趣を異にしている。
白装束の集団は、どこか宗教的な儀式を思わせる出で立ちであり、組織的に動いていたようにさえ見える。
その存在が「消えた」崖は、まるでこの世とあの世の境界線であったかのようである。
また、「しゃらんこ」という妖怪の出現は、この地に残された未練や呪詛が形を成したものとも考えられる。
首のない武士が夜な夜な馬を駆り、鈴の音を響かせながら彷徨うさまは、果たせなかった使命への執着か、あるいは誰かを探し求めているのかもしれない。
撫養城跡は、歴史的にも謎が多く、城主の変遷や築城の詳細が定かではない点も、この地に漂う“得体の知れない何か”を裏付けている。
霊的存在とは、往々にして歴史の空白に忍び込むものである。
この地に秘められた過去が、今もなお霊として顕現しているのだとすれば――訪れる者は決して油断してはならない。
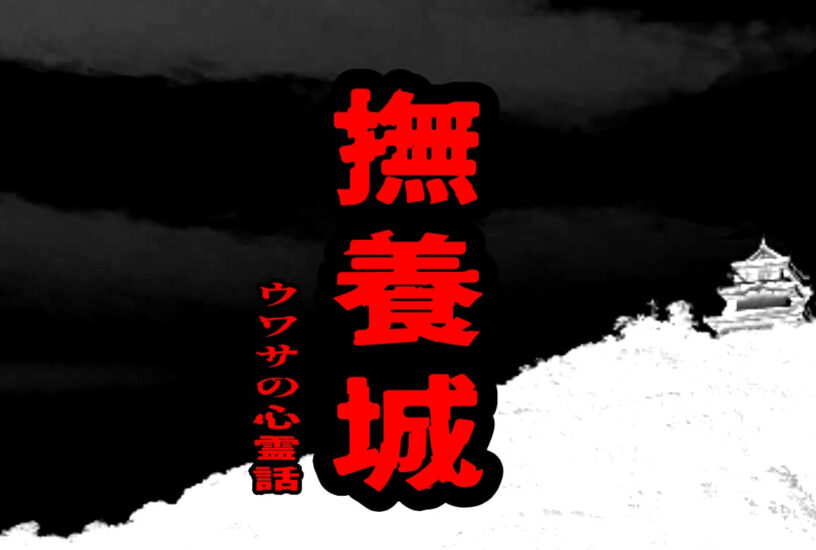

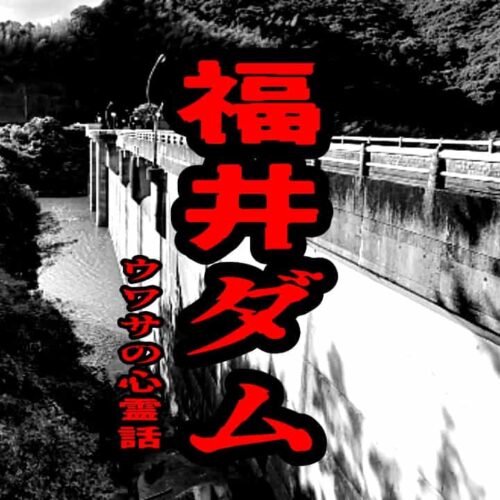
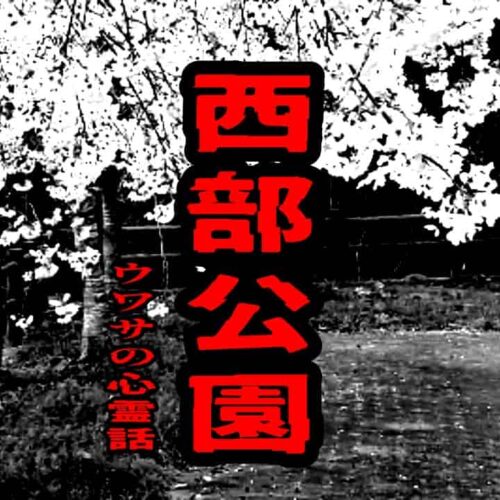

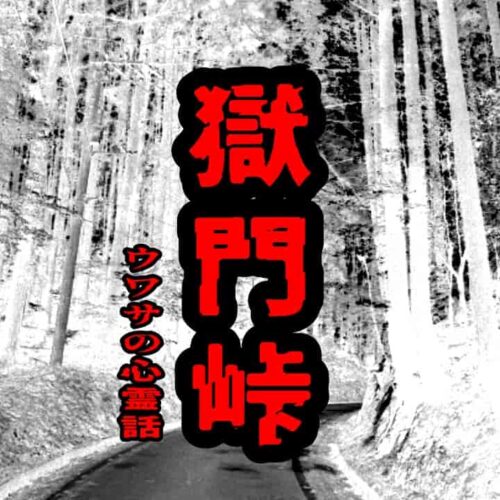
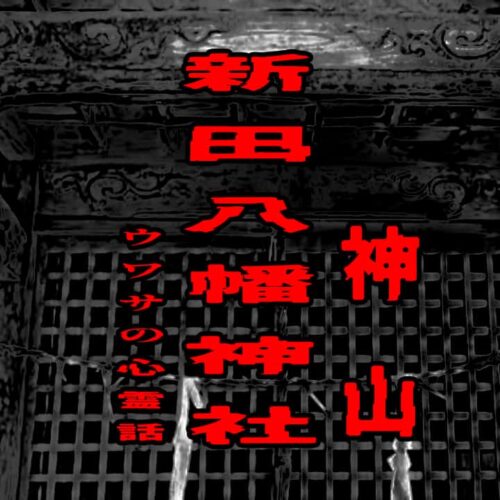
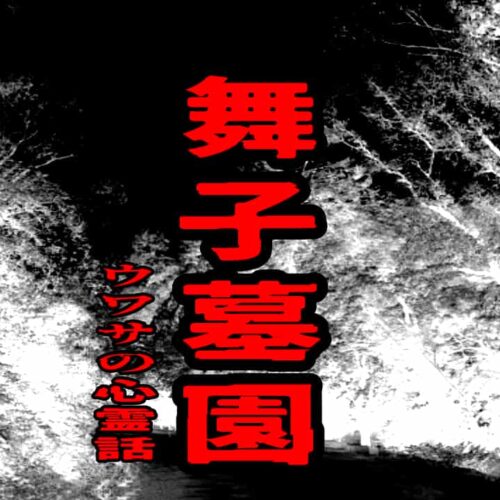
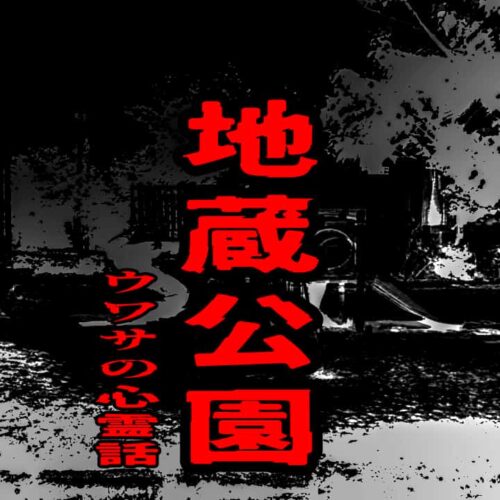
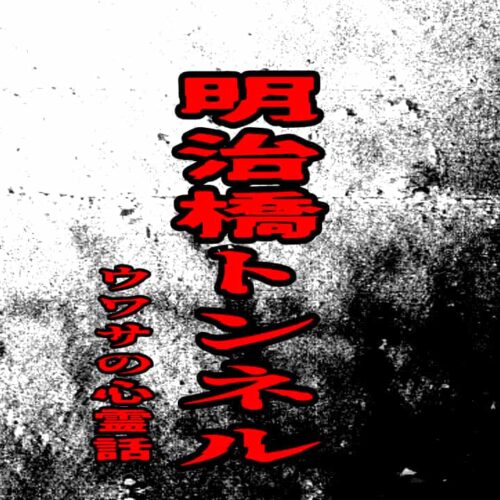
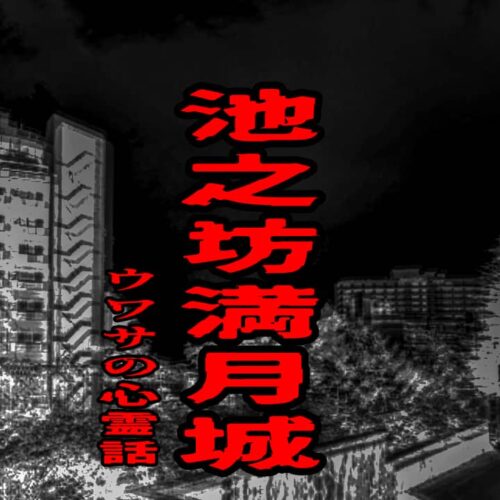
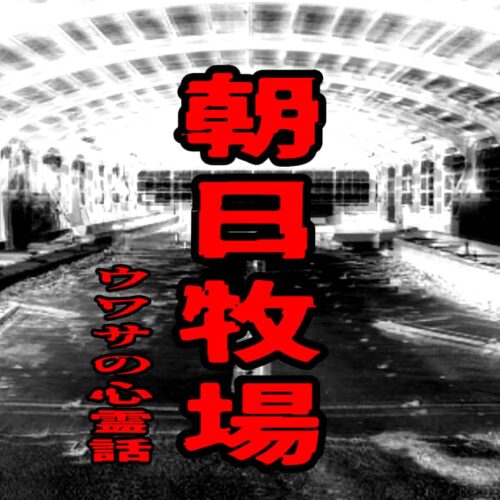
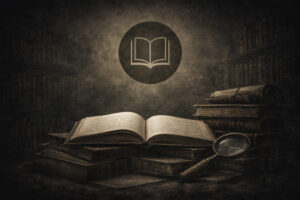
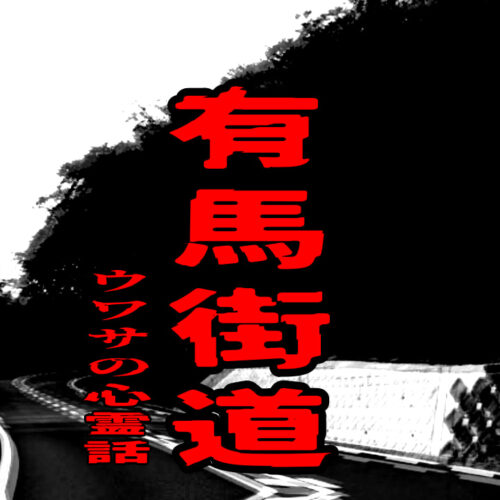
コメント