神奈川県・相模原市の山中にひっそりと佇む「育霊神社」は、古くから“祟り”や“不気味な噂”が絶えない心霊スポットとして知られている場所である。今回は、石手寺にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
石手寺とは?

石手寺(いしてじ)は、愛媛県松山市に所在する真言宗豊山派の古刹である。
熊野山、虚空蔵院と号し、本尊は薬師如来である。四国八十八箇所霊場の第五十一番札所にあたり、遍路の元祖とされる衛門三郎再来の伝説とも深く関わっている。
寺伝によれば、神亀5年(728年)、伊予国の太守・越智玉純が夢告によってこの地を霊地と悟り、熊野十二社権現を祀ったことに始まる。
その後、行基が薬師如来を刻んで安置し開基、弘仁年間には空海が訪れ、真言宗の寺院へと改められた。
最盛期には六十六坊を数える大寺院として栄えたが、永禄9年(1566年)の兵火により多くを失った。
しかし、本堂・仁王門・三重塔などは焼失を免れ、現在も荘厳な姿を残している。
道後温泉から近いこともあり、参拝者は多く、初詣・厄除け参拝者数は県内随一である。
石手寺の心霊現象
石手寺の心霊現象は、
- 夜に境内を歩くと、老婆の声で話しかけられる。振り返ると、そこには誰もいない
- 神社の階段を登ると、自分の後ろから足跡がついてきたり、不気味な声が聞こえる
- 参拝の帰りに体調を崩す人が後を絶たない
- 境内奥の「マントラ洞窟」では、闇の中から経文が聞こえ、足元に無数の影がまとわりつくように感じる
である。以下、これらの怪異について記述する。
まず「老婆の声」の怪異である。
夜に参拝すると、耳元でかすれた老婆の声が囁き、振り返った瞬間には誰もいないという。
まるで来訪者を試すかのように、執拗に呼びかけてくるといわれる。
神社の階段ではさらに異様である。
背後から足跡がついてくる音が響き、振り向いても無人。時には階段の途中で低いうめき声が混ざることもあるとされ、恐怖は倍増する。
また、石手寺を訪れた人々の中には、帰宅後に体調を崩す者が少なくない。
「厄を落とすはずの寺なのに、逆に不調をもらってしまう」と語られることすらある。
その理由については、寺の仏が強大すぎる力で人を試しているのか、あるいは寺そのものに合わぬ者を拒絶しているのか、真相は不明である。
そして、最も恐怖を誘うのが「マントラ洞窟」である。洞窟内は闇が濃く、壁に触れなければ進めぬほどに暗い。
進むにつれ、仏教の経文がどこからともなく響き、壁際には数多の地蔵が立ち並ぶ。
人によっては足元に無数の気配を感じ、影が絡みつくような感覚に襲われる。
洞窟を抜けると一度外に出されるが、戻るには再び同じ洞窟を通らねばならず、その間、異界に迷い込んだような錯覚を味わうことになる。
石手寺の心霊体験談
ある参拝者は毎年、初詣で弟に連れられて石手寺を訪れていた。
しかし、ここ二年ほどは必ず参拝の後に体調を崩すという。
「石手寺が怖いのは、守護している仏の力があまりにも強烈だからではないか」と本人は語る。
だが同時に、「自分が石手寺に合っていないのかもしれない」とも感じている。
「厄落としのために訪れたはずなのに、逆に気持ち悪さを背負って帰ってきてしまう」との言葉は、寺の異質さを物語っている。
石手寺の心霊考察
石手寺は単なる観光寺院ではなく、遍路においても特別な意味を持つ聖地である。
そのため、寺に漂う霊的な力は他の寺院に比べても格段に強いと考えられる。
老婆の声や階段での足音は、衛門三郎再生の伝説に絡む魂の残響か、あるいは寺に入り込んだ無数の参拝者の想念が形を取ったものかもしれない。
参拝者が体調を崩すという現象は、寺が人を選ぶ証左ともいえよう。
強力な仏の力に耐えられる者だけが浄化され、そうでない者は拒絶される。
その境目に立たされるとき、人は「気持ち悪さ」や「不調」という形で応答を受け取るのだろう。
そして、マントラ洞窟は石手寺の中でも最恐の存在である。
暗闇と経文、無数の地蔵が織りなす異界の空気は、まさに人の魂を揺さぶる。そこでは幽霊そのものが現れずとも、訪れた者の心を確実に試し、恐怖を刻み込む。
石手寺は“観光地として賑わう聖地”の裏に、“選ばれぬ者を拒む霊域”という顔を隠しているといえるだろう。

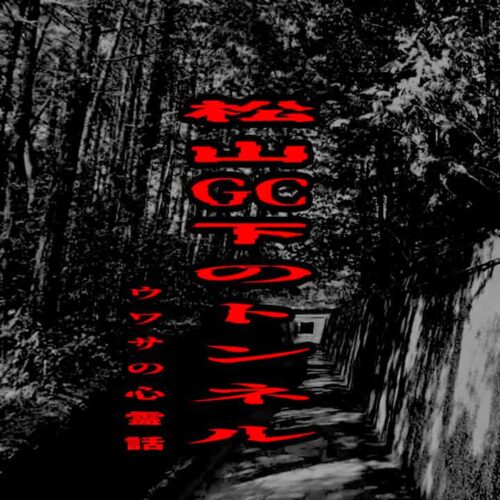
のウワサの心霊話-500x500.jpg)


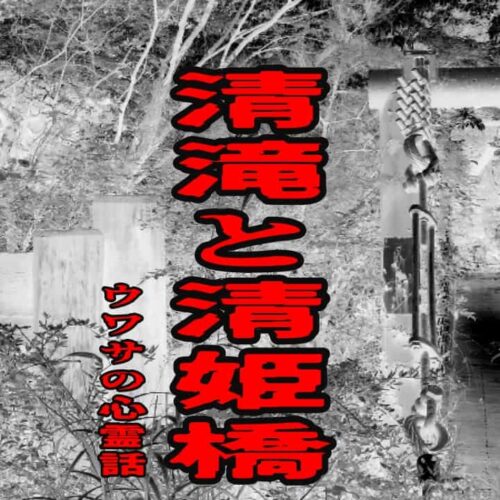
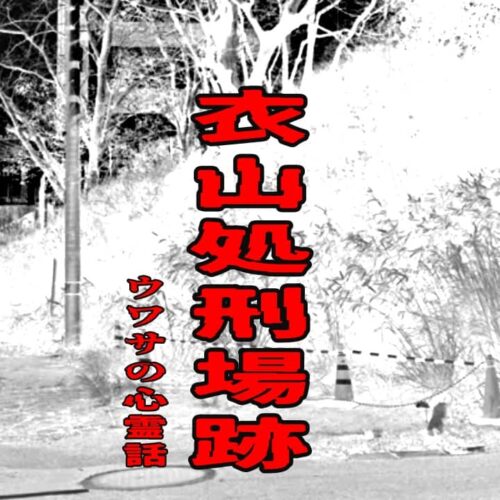
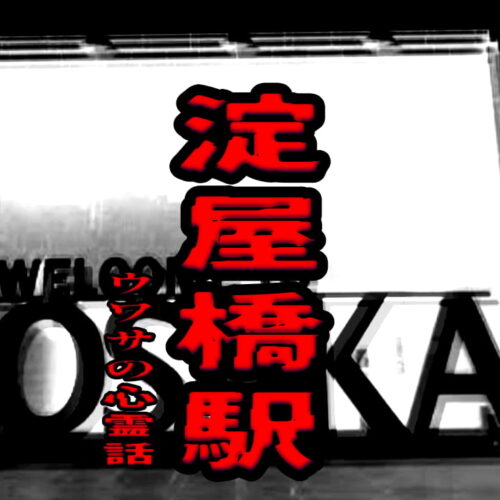
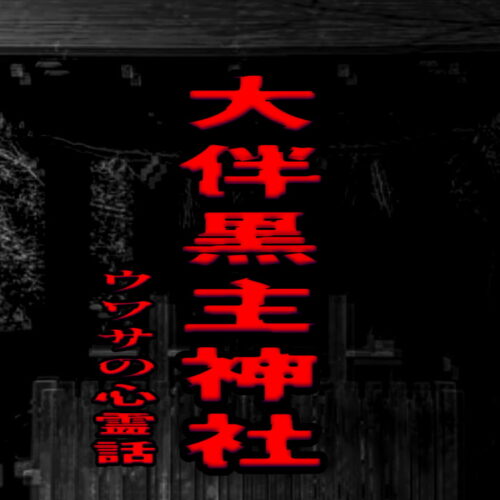
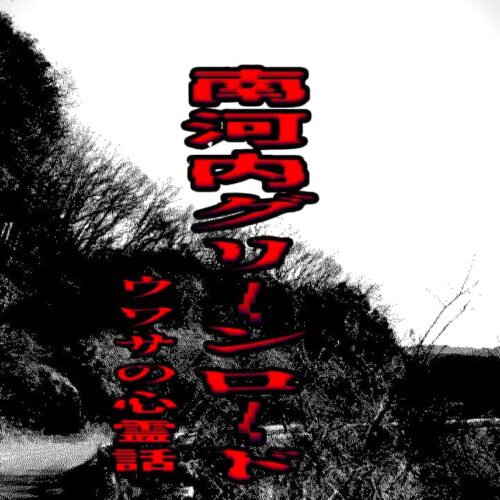
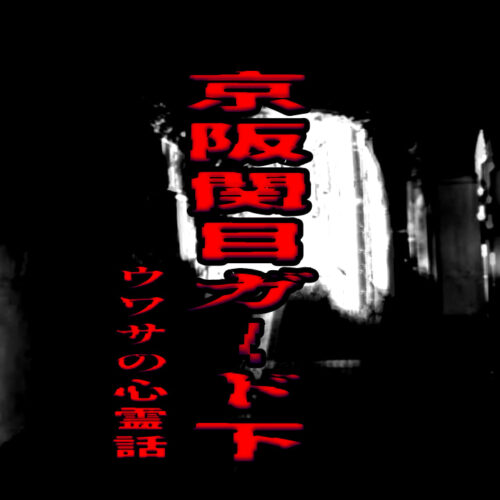

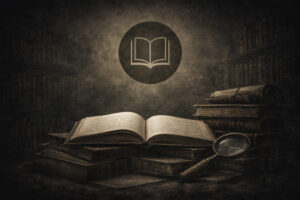
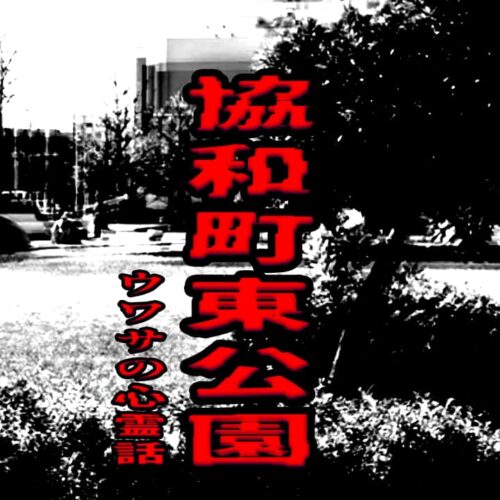
コメント