徳島市丈六町にある古刹・丈六寺には、血で染まった過去と、それにまつわる数々の怪異が今なお語り継がれている。天井に残る血痕、突然の頭痛、現れる霊──。今回は、丈六寺にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
丈六寺とは?

丈六寺(じょうろくじ)は、徳島県徳島市丈六町に位置する曹洞宗の寺院であり、正式名称を瑞麟山 慈雲院 丈六寺という。
創建は白雉元年(650年)と伝えられ、その始まりは関東から来た一人の尼僧がこの地に庵を構えたことに起因するとされている。
中世には、阿波国の守護・細川成之によって中興され、宗派は曹洞宗へと改められた。
江戸期には徳島藩主・蜂須賀家の庇護のもと整備され、多くの文化財を有することから「阿波の法隆寺」とも称されている。
境内には歴代藩主や重臣の墓も点在しており、時代の重みと静けさを漂わせている。
だが、この寺院には、静寂と歴史の美しさとは裏腹に、血と裏切りが染みついた“ある事件”の名残が今も残されている。
丈六寺の心霊現象
丈六寺の心霊現象は、
- 血痕の手形や足形が今もなお天井に残る
- 天井を見上げると、頭痛や吐き気を催す者が現れる
- 男性の霊が、徳雲院前の回廊付近に立ちすくんでいる
- 深夜、回廊で足音やすすり泣く声が聞こえることがある
である。以下、これらの怪異について記述する。
丈六寺の“血天井”は、戦国時代の謀略によって生まれた。
天正9年(1581年)、土佐の覇者・長宗我部元親は阿波への侵攻を進める中で、牛岐城主・新開入道道善(しんかい どうぜん)の存在を脅威と見なした。
元親は表向きには和議の席を設けると称し、道善主従を丈六寺に招いて酒宴を開いた。
宴が盛り上がり、道善らが帰ろうとしたその時、元親の刺客が襲いかかる。
狙われた道善と家臣たちは応戦したが、多勢に無勢、非情にも全員がその場で斬殺された。
この斬殺の痕跡は凄惨を極め、縁側の板には血痕や手形・足形が無数に残されたという。
いくら洗ってもその痕は消えることなく、最終的にその板は徳雲院前の回廊の天井板として流用された。
現在でもその天井には、血の跡と思しき茶褐色の痕が残されており、訪れた者の中には原因不明の頭痛や吐き気を訴える者も少なくない。
霊感を持つ者は「この場所は、次元の狭間が開いている」と口を揃え、現実と非現実が入り交じるような、言い知れぬ気配を感じるという。
丈六寺の心霊体験談
ある女性は、観音堂を参拝した際、「ここはこの世ではない空間に繋がっている」と語った。
彼女は全国の観音霊場を巡る者であったが、この丈六寺の奥にある観音堂で感じた“異質さ”は、かつてないものだったという。
「空間が歪んでいた。参拝者が正気で帰れるのか不安になった」と語るその表情は真剣であり、観音像の前で思わず“清めの儀”を行ったほどであった。
また、別の訪問者は、回廊を歩く最中、背後に明らかな足音を聞いた。
振り返っても誰もおらず、手には冷たい汗がにじんでいたという。
視線を上げた時、天井の血痕と目が合ったように感じた瞬間、激しい頭痛に襲われ、その場に立っていられなくなったとのことである。
丈六寺の心霊考察
丈六寺の心霊現象は、単なるウワサでは片づけられない“物的痕跡”を有している点で特異である。
血天井に残る血痕は、実際に肉眼で確認することができ、またその場で体調に異変をきたす者が後を絶たない。
考えられる原因の一つは、無念の死を遂げた新開道善らの怨念が、浄化されずに天井板へと宿ったことであろう。
寺という霊的に開かれた場所であったことも相まって、その怨霊は地に還ることなく今も留まり続けていると推察される。
また、観音堂における“異空間の接触”とも言うべき体験談は、丈六寺が単なる歴史遺構ではなく、“何か”と繋がる場である可能性を示唆している。
丈六寺は、歴史と信仰の場であると同時に、いまだ鎮まりきらぬ“叫び”が残る地でもある。
その声に耳を傾ける覚悟がある者だけが、真の丈六寺を体感することができるのかもしれない。
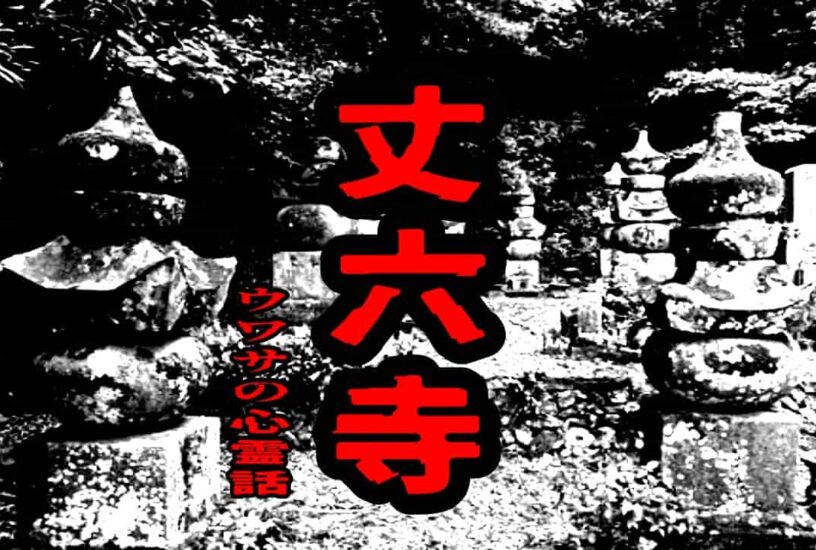
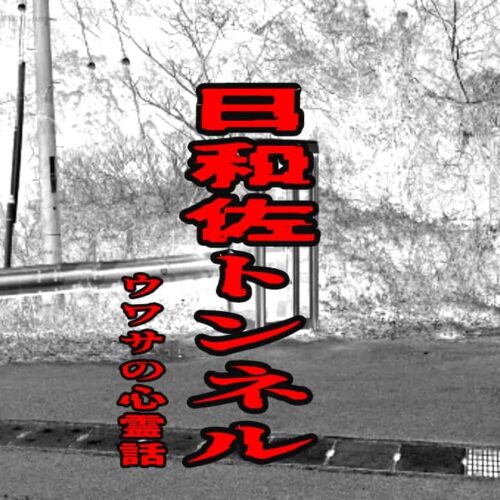
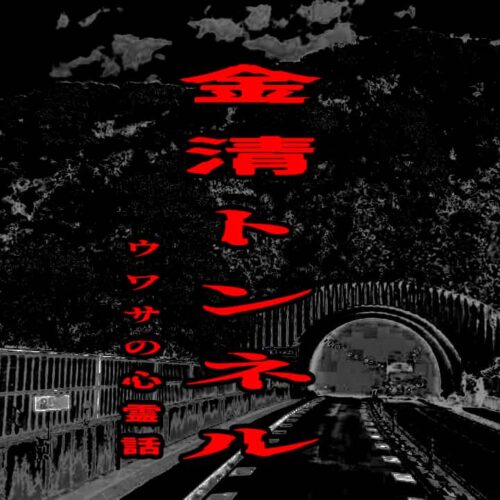
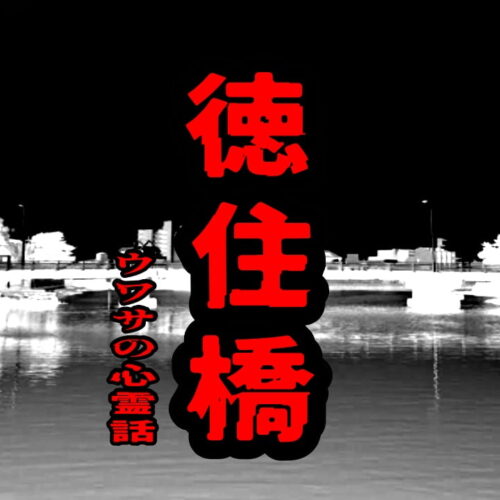
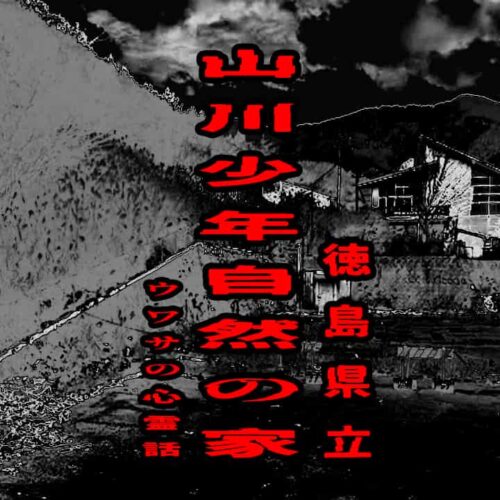
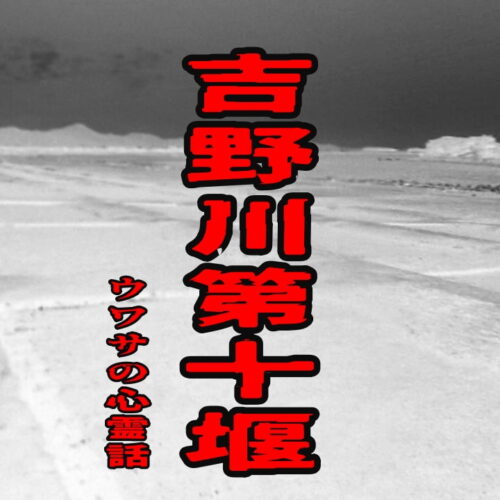
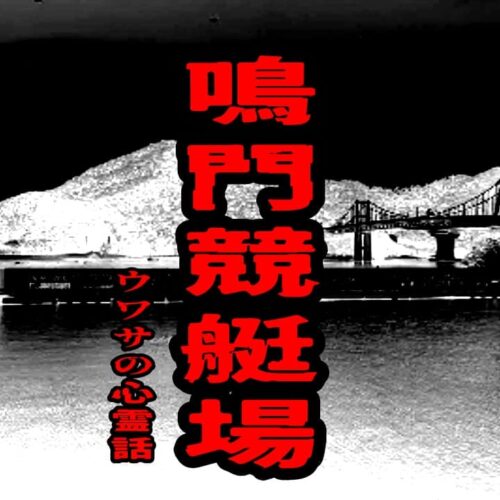
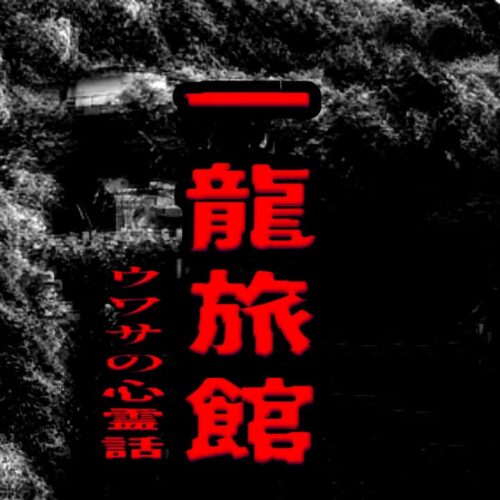
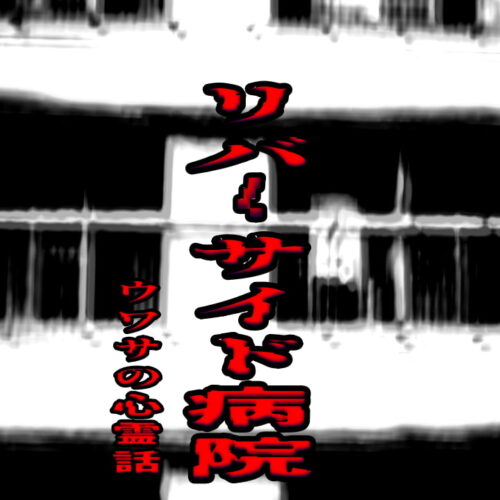
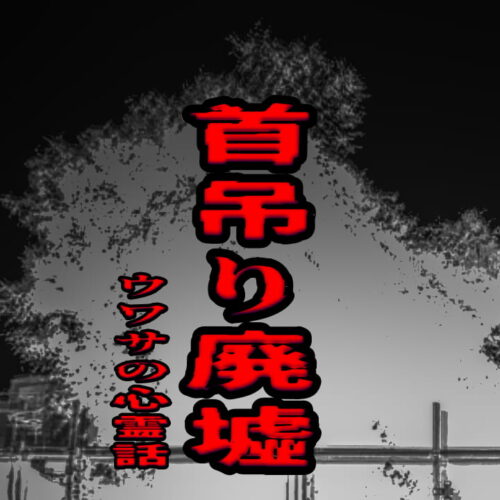
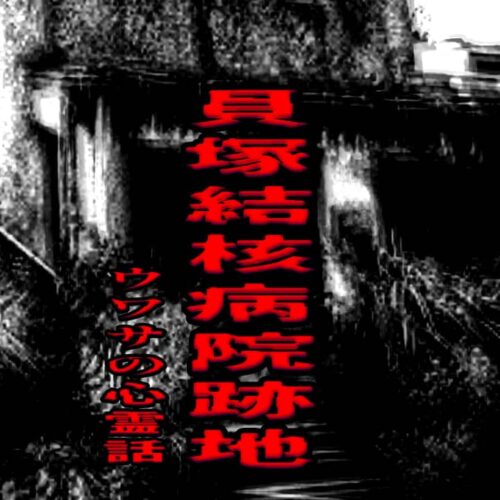
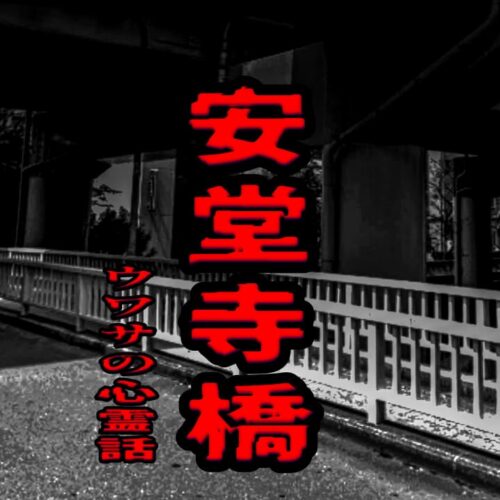
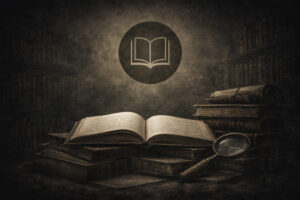
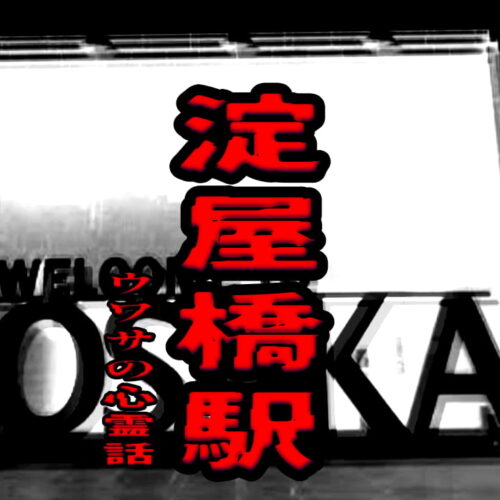
コメント