山口県宇部市にひっそりと残る、歴史的な石畳道「千林尼石畳道」。かつての峠道に敷かれたその石の上には、今もなお不可解な影が蠢いているという。今回は、千林尼石畳道にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
千林尼石畳道とは?

千林尼石畳道は、山口県宇部市とその周辺の厚東、船木方面を結ぶ旧街道の一部であり、江戸末期に整備されたとされる歴史的な道である。
この道はかつて、毛利藩の勘場(現在の役所)であった船木と、厚東、さらには宇部方面をつなぐ主要幹線のひとつであった。
しかし、その経路は険しい峠越えを要する難所であり、人や馬が行き交うにはあまりに過酷な山道であった。
この困難な状況を見かねたのが、「千林尼」という一人の尼僧である。
彼女は自ら托鉢して浄財を集め、安政4年(1857年)頃より道の整備を始め、慶応年間(1866年前後)には一部の難所に石を敷き詰めるなど、まさに現代の舗装道路とも言える石畳を築いたという。
千林尼は宇部市西岐波大沢の出身であり、16歳で結婚するもほどなく離縁し、仏門へと入った。
後年は船木の逢坂観音堂の堂守として活動し、晩年は玉泉庵に移って明治2年(1869年)にこの世を去った。
その生涯はまさに慈悲と献身に満ちたものであったが、今、彼女の築いたその道は、異なる意味で人々を惹きつけている――。
千林尼石畳道の心霊現象
千林尼石畳道の心霊現象は、
- 夜中にひとりで歩くと、背後から足音が聞こえる
- 道端の木陰に、白装束の女が立っていたという目撃談
- 石畳の上に、突然人影が現れては消える
- 急に空気が重くなり、動悸や吐き気を訴える者がいる
である。以下、これらの怪異について記述する。
千林尼石畳道は、現在では一部が民家の間にわずかに残されているに過ぎない。
だが、その短い距離でさえ、どこか時間が止まったかのような異様な空間である。
まず、深夜に通行すると足音が後をついてくるという現象についてだが、実際には誰も後ろにはいない。
振り返っても何もなく、音だけが確かにそこに存在するという。
そしてその音は、まるで草履を引きずるような、時代がかった足音であるという証言が多い。
また、白装束の女が木陰に立っていたという目撃談は、複数の地元住民によって語られている。
女はじっと前を見つめており、声をかけるとフッと消えてしまうのだという。
その姿にはどこか尼僧のような雰囲気があったという証言もある。
石畳の道の上に人影が現れるという現象もまた、繰り返し語られてきた。
薄暗い夕方や夜明け前、遠くに誰かが立っていると思い近づくと、影はすっと霧のように消えるという。
さらに、不思議な身体症状も報告されている。
道に足を踏み入れた途端に、急激な胸の締めつけや吐き気、手足のしびれなどを訴える人も少なくない。
その場所には何か見えない「念」が宿っているとしか思えない現象である。
千林尼石畳道の心霊体験談
ある地元住民の証言によれば、夜に犬の散歩でその道を通った際、急に犬がうなり声をあげて動かなくなったという。
そして、その場から離れようとした時、茂みの奥から誰かが覗いているような気配を感じた。
ライトを当てても何も見えず、しかし明らかに「何か」がそこにいたと語っている。
また、別の人物は早朝にジョギング中、石畳に差し掛かった瞬間、道の真ん中にぼんやりと立つ女性を見たという。
声をかけようとしたが、声が出ず、恐怖にかられて引き返したところ、女性はそのまま溶けるように消えたという。
千林尼石畳道の心霊考察
千林尼石畳道に残る数々の心霊現象の背景には、千林尼自身の強い執念と、数多くの人々の苦労と祈りが染みついている可能性がある。
彼女の慈悲深き行為は称賛に値するが、そのような大義の裏には、修行や托鉢により蓄積された「念」や、「死」に近い行としての重みが残留していても不思議ではない。
また、道を行き交った人々の中には、旅の途中で命を落とした者、病に倒れた者も多かったであろう。その無念や未練が、今なお石畳の隙間から漏れ出ているのかもしれない。
歴史的価値の高いこの石畳道であるが、夜に立ち入ることは決しておすすめできない。
そこには、時を超えてなお消えぬ気配と、かつての人々の記憶が、静かに、そして確かに、息づいているからである。
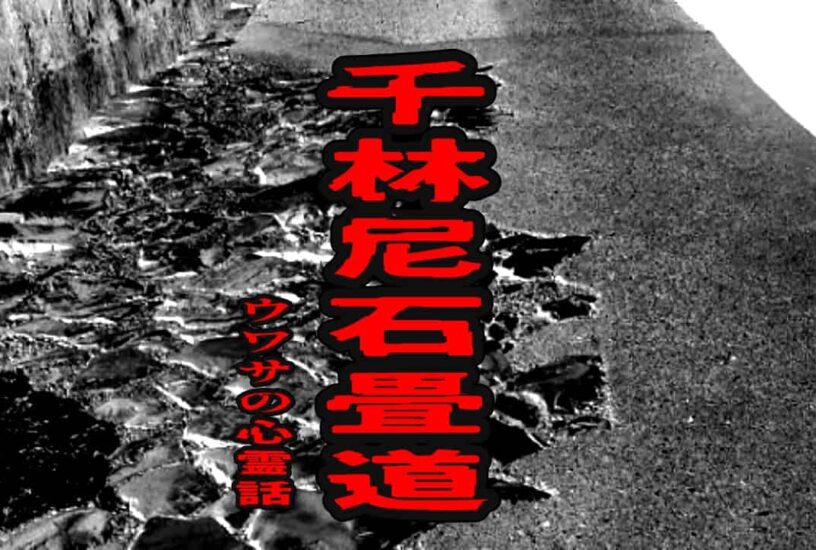
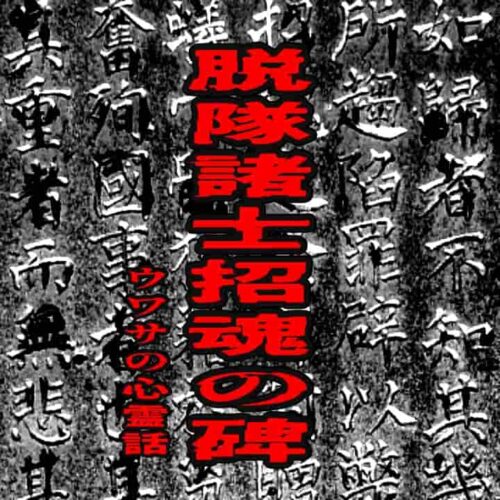
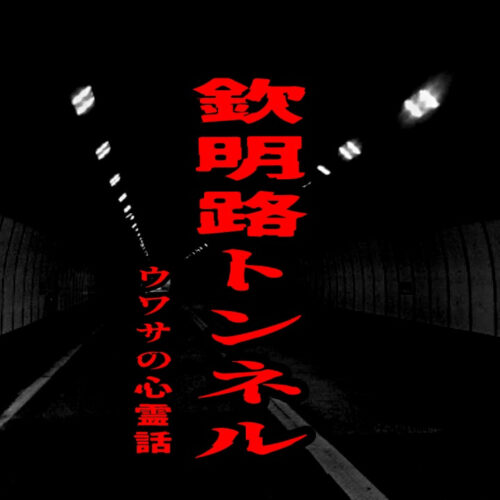
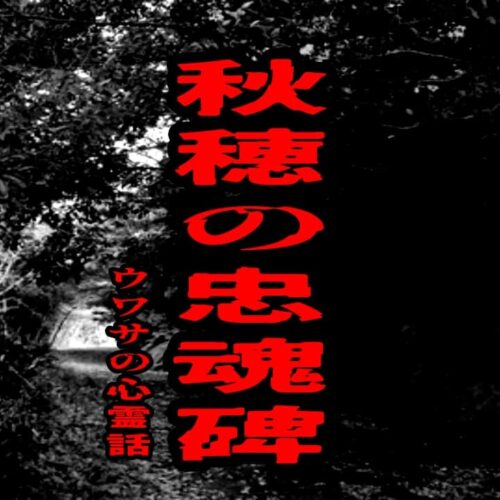
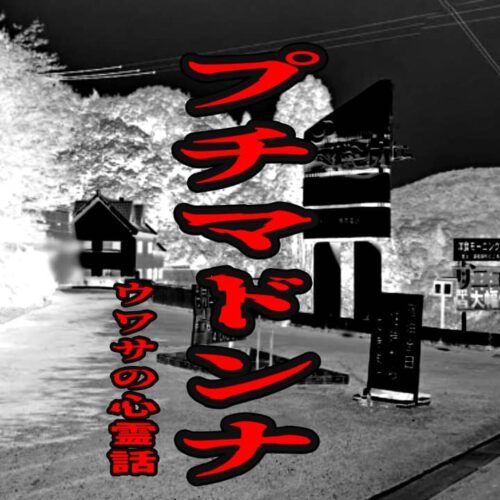
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
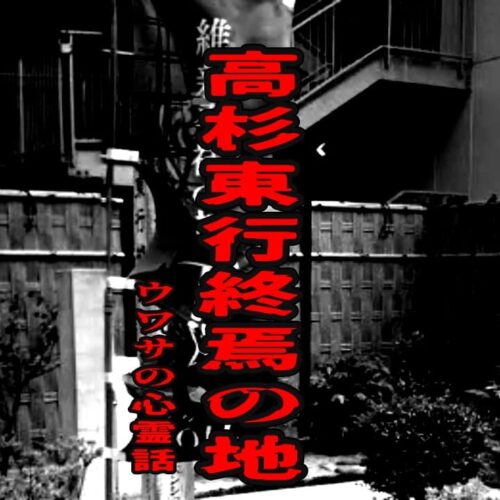
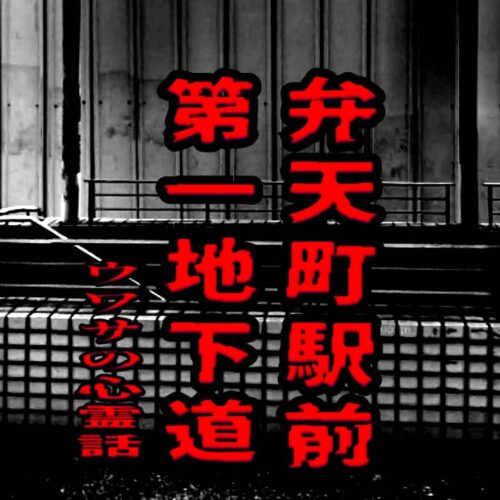
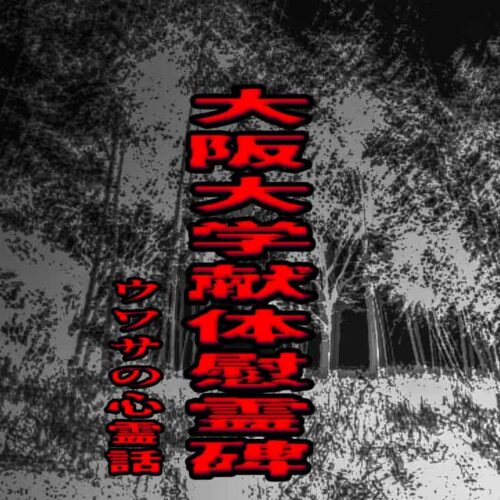
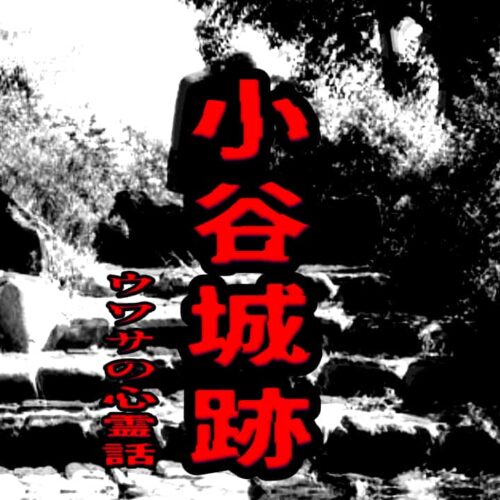
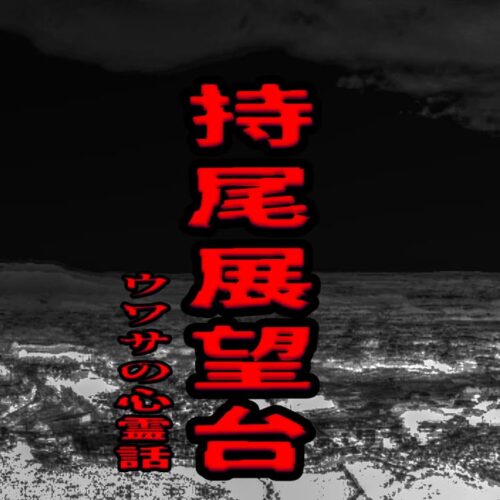
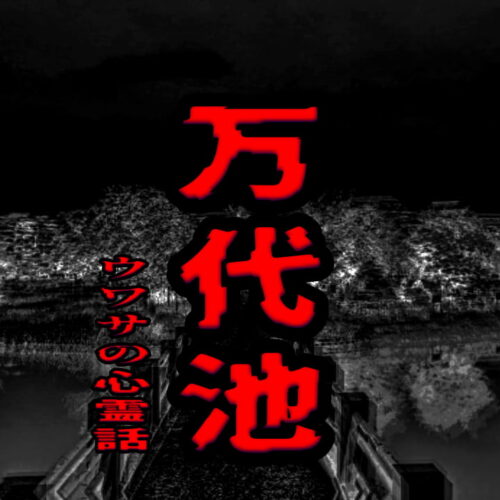
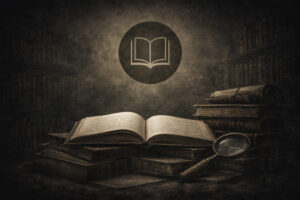
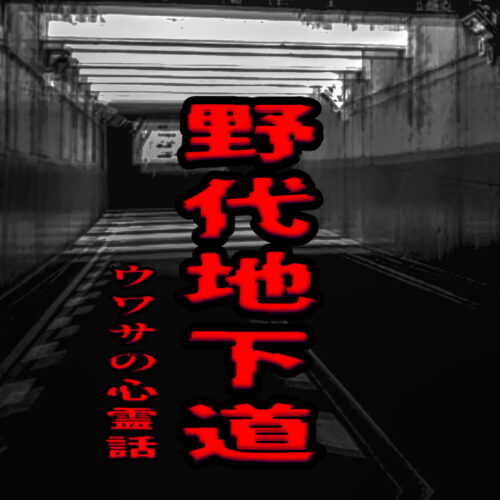
あの道は短いので途中で遭難とかはまず無い
ジョギングとか散歩とかする人はまず居ない
石畳は道祖神に護られてけがれは無い
あるとすれば出口側の施設跡が原因だろう