四国八十八ヶ所霊場の第十九番札所・立江寺には、罪を抱えた者が足を踏み入れると不思議な現象に見舞われるという、古くからの恐ろしい言い伝えが存在する。とりわけ「肉付鐘の緒」と呼ばれる実在の遺物には、生々しい事件と因縁が絡んでおり、今なお訪れる者の心に強烈な畏怖を刻む。今回は、立江寺にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
四国八十八ヶ所霊場 第19番札所 立江寺とは?
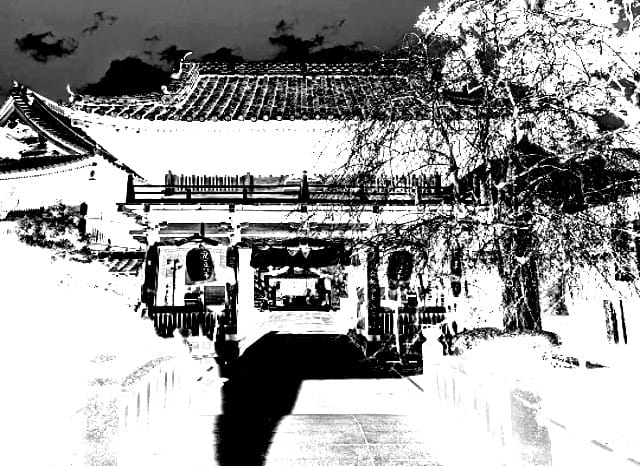
立江寺(たつえじ)は徳島県小松島市にある高野山真言宗の古刹である。
その起源は天平19年(747年)に遡り、聖武天皇の勅命により光明皇后の安産祈願のため、行基菩薩が建立したとされている。
本尊は延命地蔵尊。弘法大師(空海)が当時の小さなご本尊では紛失の恐れがあるとして、自ら6尺(1.8m)の大像を刻み、その胎内に小像を納めたという逸話が残る。
また、立江寺は四国八十八ヶ所の中でも重要な位置を占める「関所寺」として知られている。
関所寺とは、罪や邪念を抱く者が通過できないとされる霊的関門であり、立江寺はその最初の関門とされる。
四国八十八ヶ所霊場 第19番札所 立江寺の心霊現象
四国八十八ヶ所霊場 第十九番札所・立江寺の心霊現象は、
- 鐘の緒に絡みついた“人間の髪”が実在する
- 境内で女のすすり泣きが聞こえる
- 地蔵尊に手を合わせると急に体調が悪くなる
- 罪を隠して巡礼に訪れると奇怪な現象に襲われる
である。以下、これらの怪異について記述する。
肉付鐘の緒とお京の悲劇
立江寺には「黒髪堂」と呼ばれる小堂があり、その内部には、実際に黒髪が巻き付いたままの「鐘の緒」が安置されている。
この髪は、江戸時代に“お京”と呼ばれた女が体験した恐ろしい現象の痕跡である。
お京は島根県浜田で生まれ、大阪へ売られて芸妓となった。その後、夫となった要介と故郷に戻ったが、鍛冶屋・長蔵と不義密通を重ね、最終的に要介を殺害。
逃避行の末、死にきれずに四国遍路へと逃れた二人は、立江寺に至る。
ここで事件は起きた。地蔵尊に礼拝しようとしたお京の髪が突如逆立ち、鐘の緒に巻き付き、まるで地獄の審判のようにその身体を吊り上げていった。
叫び声と共に髪と頭皮が剥がれ落ちるという惨劇を前に、住職が罪の有無を問うと、お京はすべての悪行を白状した。
その懺悔と共に、鐘の緒に絡みついた黒髪はそのまま抜け落ちず、現在に至るまで“肉付鐘の緒”として保管されている。
黒髪堂の異様な気配
黒髪堂の前に立つと、空気が変わる。
とくに夕刻に近づくと、人の気配とは異なる何かが堂内からこちらを覗いているような錯覚に陥る。
多くの参拝者が、堂の前で突然寒気を覚えたり、背後から誰かに見られているような感覚を訴えている。
四国八十八ヶ所霊場 第19番札所 立江寺の心霊体験談
ある巡礼者の話である。
彼は地蔵尊の前で手を合わせた瞬間、頭の中に「許さない」という声が響いたという。
その後、黒髪堂に立ち寄った際、堂内から女の泣き声がはっきりと聞こえ、あまりの恐怖に足がすくんで動けなくなったという。
また別の人物は、黒髪堂を撮影しようとカメラを構えたところ、シャッターが何度押しても切れず、帰宅後カメラを確認すると、その日撮った写真だけがすべて消えていたと証言している。
四国八十八ヶ所霊場 第19番札所 立江寺の心霊考察
立江寺における心霊現象の多くは、「関所寺」としての役割と深く結びついている。
邪念や罪を抱えた者は、霊的な審判を受ける。肉付鐘の緒に代表される“可視化された罪の痕跡”は、現代においても霊的警告としての意味を強く保っている。
黒髪が巻き付いたまま朽ちずに残るという事実は、物理的に説明のつかない異常現象であり、信仰の対象であると同時に、訪れる者に罪と向き合うことを強いる“見えざる審問”の場となっているのだ。
偶然やオカルトとして片付けるには、あまりにも具体的で、あまりにも痛ましい。
立江寺は単なる巡礼の一地点ではなく、過去の業を浮かび上がらせ、魂を問う“四国の関所”なのである。
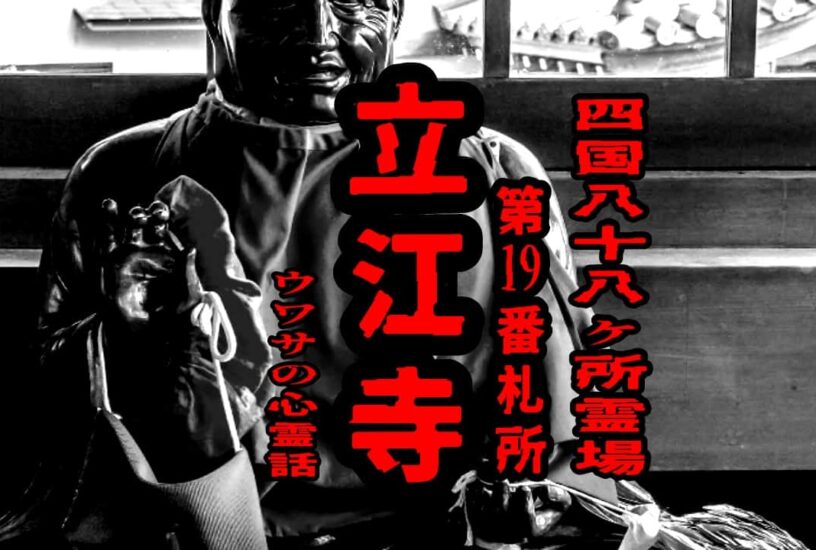

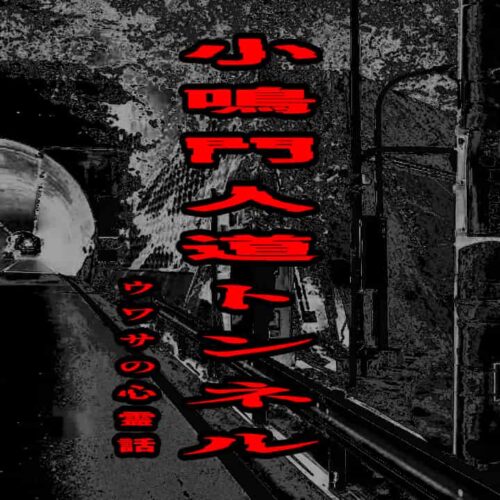

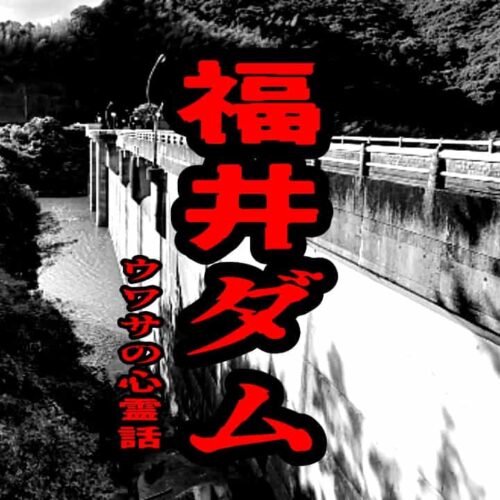
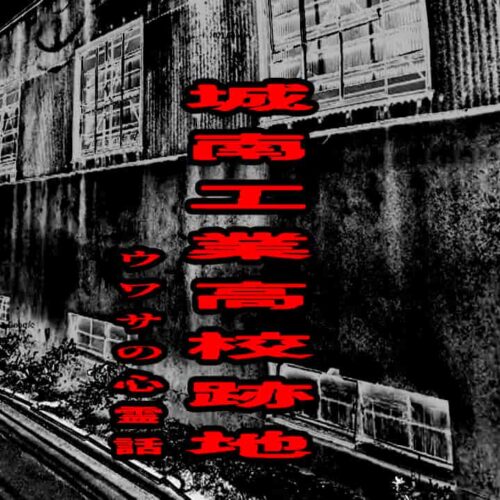

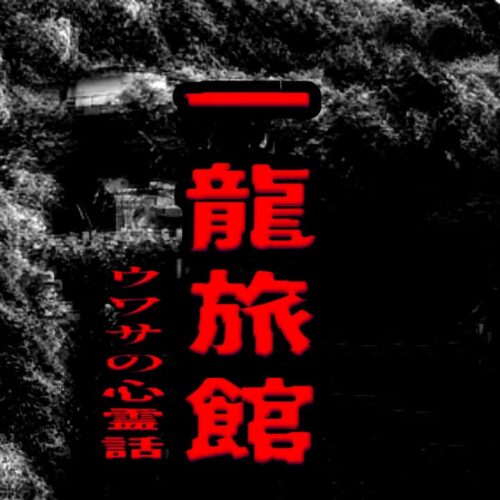
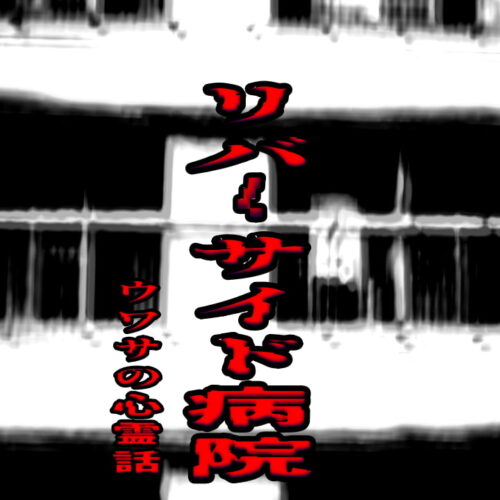
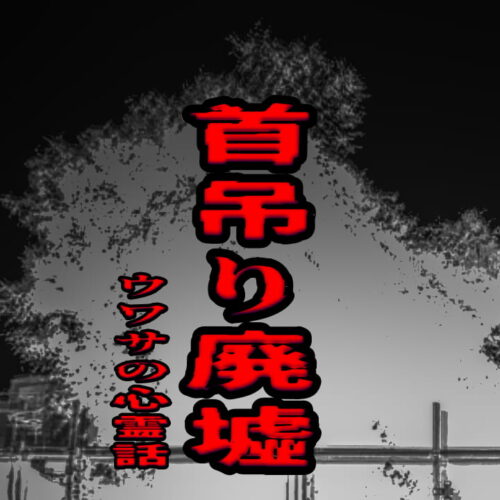
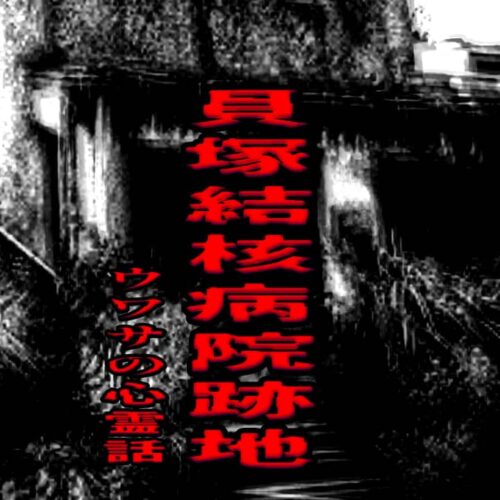
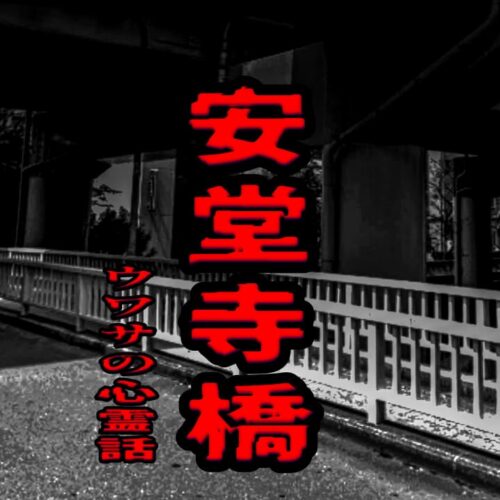
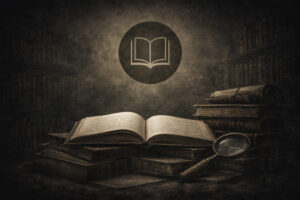
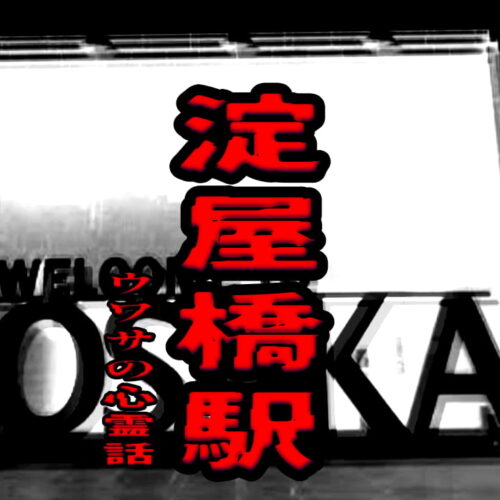
コメント