夜、家族が自宅のリビングでテレビを見ていると、玄関から「ただいま」という懐かしい声が響いた。
その声は確かに、施設に預けたはずの祖母のものだった。
誰もが耳を疑い、一瞬、時が止まったように家中が静まり返った。
「あれ、おばあちゃん帰ってきたの?」と娘の美咲が口にするが、誰も答えることができなかった。
母親の陽子は、明らかに動揺していた。
施設に預けた祖母が突然、何の前触れもなく帰宅するなど、あり得ないことだったからだ。
「きっと何かの聞き間違いよ」と陽子は言い聞かせるように言い、他の家族もそれに同意するしかなかった。
しかし、家の中に漂う奇妙な空気が彼らを不安にさせた。
その夜は、皆が何となく心ここにあらずのまま眠りについた。
次の日の朝、陽子は施設に電話をかけた。
祖母の様子が気になったからだ。
施設のスタッフが電話口に出た瞬間、陽子の心臓は早鐘のように打ち始めた。
「すみません、実は…おばあさまが昨夜亡くなられたんです。」
その言葉は、陽子の脳裏に電撃のように突き刺さった。
手が震え、電話機を落としそうになった。
「え…どうして…」
祖母が亡くなった時間は、ちょうど家族が「ただいま」という声を聞いた時刻と一致していた。
家族全員がその事実を知ったとき、何とも言えない寒気が全員を包み込んだ。
誰もが無言で、その夜の出来事を思い返し、ただ恐怖に怯えるしかなかった。
だが、それで終わりではなかった。
その夜、再びリビングで家族が集まっていると、再び玄関から「ただいま」という声が響いた。
今度は全員が確実に聞いた。母親は涙を流しながら、「おばあちゃん、もう安らかに眠って…」と呟いたが、声は消えなかった。
それどころか、その声は日々頻繁に聞こえるようになり、家中に響き渡るようになった。
何度も祈りや供養を試みたが、祖母の声は止むことはなかった。
家族は次第に精神的に追い詰められ、家を出ることを考え始めた。
だが、その家を去ることができる者は誰もいなかった。
まるで祖母の声が、家族全員をその場所に縛り付けているかのようだった。
そしてある日、家族の一人がふと鏡を見ると、そこには祖母の姿が映っていた。
その目は、何かを訴えかけているようで、そこにはただならぬ怨念が感じられた。
その瞬間、家族は理解した。
祖母は何かを求めてこの世に戻ってきたのだと。
しかし、その「何か」が何であるのか、誰にもわからなかった。
それから数年、家族は祖母の声と共に生き続けたが、次第にその声は静かになり、最終的には消え去った。
だが、家族は今でも時折、夜の静寂の中で、かすかに聞こえる「ただいま」という声に耳をすませることがある。
祖母が何を求めていたのか、それは永遠に謎のままだが、その声が家族の記憶に深く刻まれ、彼らは決してその家を出ることができなかった。








のウワサの心霊話-500x500.jpg)
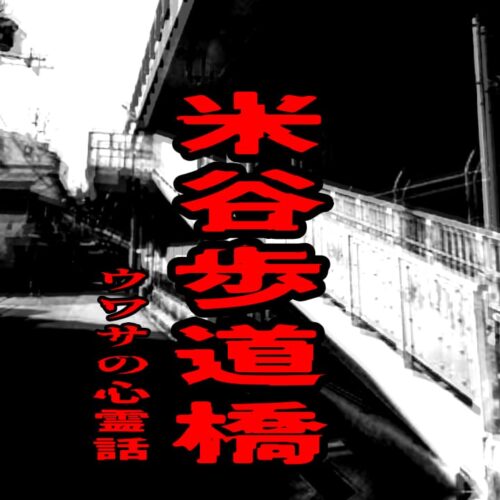
のウワサの心霊話-500x500.jpg)



コメント