お盆の夜、静かな自宅で一人過ごしていた。
家族は皆、旅行や仕事で外出しており、誰もいないはずだった。
窓の外では、虫の音が夜の静けさをかすかに破るだけで、街は眠りについたかのような静寂に包まれていた。
午後11時を過ぎ、ようやくベッドに入ろうとしていたその時、突然インターホンが鳴り響いた。
「こんな時間に?」と疑問が頭をよぎるが、インターホンのモニターを確認してみると、そこには誰も映っていなかった。
画面にはただ真っ暗な玄関先が広がっているだけだった。
「故障かな…」と思いつつも、心のどこかで違和感を感じた。
念のため玄関のドアを開けてみるが、外には誰もいない。
通りには明かりもなく、夜風が肌寒く感じるだけだった。
しかし、ドアを閉めようとしたその瞬間、家の中に生温かい風がゆっくりと流れ込んできた。
まるで見えない何かが家の中に入り込んだかのように。突然、全身に寒気が走り、背筋が凍る感覚に襲われた。
風が吹いているわけではないのに、部屋の空気が妙に重くなり、嫌な気配が漂っている。
「誰かが…いる?」
心臓が激しく鼓動を打ち、周囲を見渡すが、もちろん誰もいない。
それでも、どこかで見えない視線を感じていた。
慌ててドアを閉め、すぐに鍵をかけたが、その不快な気配は消えることなく、家の中を包み込んでいた。
何かがいる。
はっきりとは言えないが、その場にいるはずのない者が、確かに近くに存在しているのを感じた。
全身が凍りつくような感覚に耐えられず、俺は布団の中に潜り込んだが、寝つくことなどできるはずもなかった。
翌朝、恐る恐る玄関を確認すると、目に飛び込んできた光景に言葉を失った。
玄関前の地面には、いくつもの見覚えのない足跡が、無数に散らばっていたのだ。
それは、人の足跡に見えたが、誰のものでもなかった。
家に来るはずのない訪問者が、夜中にここに立ち、そして消えていったことを示しているかのようだった。
「昨夜のインターホン…まさか…」
その足跡が意味するものを考えると、寒気が再び背中を這い上がってきた。
あの生温かい風、そして、見えない何かが家の中に侵入した感覚。
何か、呼んではいけない者を招き入れてしまったのかもしれない。
それ以来、俺は夜中に鳴るインターホンには決して応えないようにしている。








のウワサの心霊話-500x500.jpg)
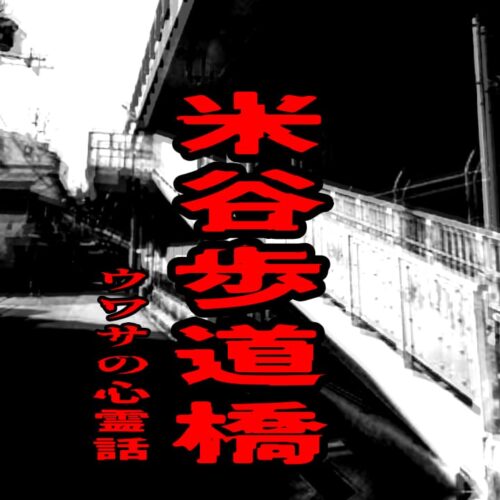
のウワサの心霊話-500x500.jpg)



コメント