お盆の夜、外は鈴虫の鳴き声が響き渡り、風も穏やかだった。
親戚一同が集まり、仏壇の前で線香を手向けながら、亡くなった祖父の思い出を語り合っていた。
父や母が当たり前のようにしているその光景を、僕は少し不思議に感じていた。
祖父が亡くなってからもう3年が経つ。
思い出すことも少なくなっていたが、この時期になると必ずこうして彼のことが話題に上がる。
「おじいちゃん、元気にしてるかな?」
子供心にそう思いながら、僕は仏壇の中をぼんやりと見つめていた。
祖父の写真が微笑んでいる。
その横には線香がゆっくりと燃えていく。
白い煙が薄暗い部屋の中で揺れながら立ち上る様子は、どこか現実感を欠いているように思えた。
しばらくして、母が小声で「そろそろ帰ろうか」と言い、家族全員が線香に手を合わせた。
誰もが静かに黙祷を捧げているその瞬間、仏壇の奥から何かが聞こえた気がした。
最初は誰も気づかなかった。まるで風の音に混じったかのような微かな声だった。
僕は耳を澄ませた。
「今の、何だ?」心臓が少しだけ早くなる。
線香の燃え尽きるまでの時間、部屋は静寂に包まれていたが、その声は確実に再び聞こえてきた。
「助けて…」僕の全身が一瞬にして凍りついた。
「え?」僕は思わず口に出した。
父が僕を見て「どうした?」と尋ねるが、僕は答えることができなかった。
確かに聞こえたのだ。
仏壇の奥から、誰かが何かを訴えている。
周りを見渡すが、他の家族は気づいていないようだ。
線香がさらに燃え進むにつれ、その声は次第に大きく、はっきりと聞こえるようになった。
「ここから出してくれ…」その言葉に僕は息を呑んだ。
間違いない。あれは祖父の声だ。確かに祖父の声だった。
僕は恐怖に駆られながらも、目を仏壇に向け続けた。
声はどんどん大きくなり、部屋全体に響き渡るようになった。
「助けてくれ…ここから出してくれ…」その瞬間、仏壇の扉がゆっくりと開きかけたように見えた。
「おい、誰か聞こえないか?」僕は焦って家族に訴えた。
しかし、誰もその声を聞いていないようだった。
線香が最後の一筋の煙を放ち、静かに燃え尽きた瞬間、声は突然、ぴたりと止んだ。仏壇の扉も動きを止め、再び静寂が戻った。
まるで何事もなかったかのように、部屋は元の静けさを取り戻したが、僕はまだ震えていた。
父が何事もなかったかのように「さあ、帰ろう」と言い、母も「明日も早いしね」と続けた。
僕は呆然としながらも、立ち上がるしかなかった。
その夜、僕は寝つくことができなかった。
あの声は何だったのか。
祖父は本当に助けを求めていたのか。
そして、なぜ僕だけがその声を聞いたのだろうか。
仏壇に閉じ込められた祖父の魂が、今もあの部屋で助けを求めているような気がしてならない。
そして翌年のお盆、僕は再び仏壇の前に座ることになった。
しかし、その時はもう、何も聞こえなかった。
ただ、あの時の恐怖が今も心に残り続けている。
仏壇に祖父の写真が微笑む度に、僕は心のどこかで、彼がまだ何かを訴えているのではないかという思いを拭い去ることができなかった。
お盆の夜は、先祖が帰ってくると言われるが、もしその帰り道が間違ってしまったら、彼らは永遠に助けを求め続けるのかもしれない。








のウワサの心霊話-500x500.jpg)
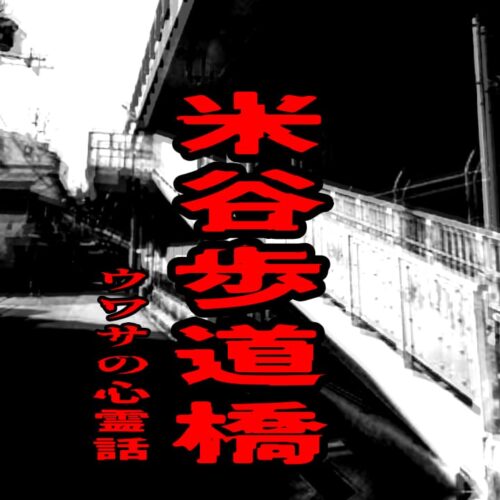
のウワサの心霊話-500x500.jpg)



コメント