愛媛県今治市にある明積寺には、「飴買い幽霊」と呼ばれる戦慄の伝承が残されている。今回は、明積寺にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
明積寺とは?

明積寺(みょうしゃくじ)は今治市北鳥生町に位置し、真言宗醍醐派に属する古刹である。
開山は慶長年間(1596〜1615年)にさかのぼり、初代住職・憲献上人によって祈祷寺として創建された。
かつては三嶋神社(祇園町)の別当寺を務め、神仏習合の時代には地域信仰の中心として厚く信仰を集めた。
江戸時代には俊範上人や学信和尚らの名僧を輩出し、荒廃しかけた寺を立て直した歴史を持つ。
本堂は幾度も再建を経ており、昭和五十五年(1980年)には現在の姿へと新築され、地域信仰の拠点として今もその存在を保ち続けている。
明積寺の心霊現象
明積寺の心霊現象は、
- 「飴買い幽霊」の出現
- 墓の下から響いた赤子の泣き声
- 三途の川の渡し賃を失った母の怨念
である。以下、これらの怪異について記述する。
江戸時代中頃、今治の町で一人の若い女性が身ごもったまま亡くなり、静かに葬られた。
だがその晩から、飴屋の前に青白い顔の女が現れるようになった。
女は毎夜、無言で一文銭を差し出し、飴をひとつ買っては闇に消えていった。
飴屋の主人・惣兵衛は奇妙に思いながらも、同じやり取りを繰り返した。
七日目の夜、女は一文銭を持たず現れ、ただ深い眼差しを向けてきた。
惣兵衛は同情し、飴を多めに渡した。
女は代わりに「樒の葉」を置き、蒼社川を渡って明積寺の境内へと消えた。
その後を追った惣兵衛は、寺の新しい墓から赤子の泣き声が漏れるのを耳にした。
墓を掘り返すと、死んだ母の腕に抱かれた赤子が生きており、その口には確かに飴がくわえられていた。
女は死してなお我が子を守ろうとし、棺に入れられた六文銭──三途の川の渡し賃を使い果たしてまで、赤子に飴を与え続けていたのである。
この赤子こそが、のちに名僧・学信和尚として名を馳せる人物であった。
明積寺の心霊体験談
明積寺を訪れた者の中には、今も夜の境内で「白装束の女を見た」という証言がある。
線香の煙が揺らめく本堂脇で、誰もいないはずの墓地から赤ん坊の泣き声を聞いたという話も残る。
幽霊が現れたとされる飴屋の子孫はいまも「縁起あめ」を販売しており、その甘さの裏には、母が死してなお子を想った怨念と愛情が染みついていると語られている。
明積寺の心霊考察
「飴買い幽霊」は、母の深い愛情と三途の川を渡れなくなった怨念が重なり生まれた怪異である。
六文銭をすべて失った彼女は、成仏することもできず、ただわが子を生かすために夜ごと飴を買い続けた。
この話が今に語り継がれているのは、学信和尚が名僧となったからである。
しかし、裏を返せば──彼の誕生には、母が地獄に取り残されるという恐ろしい代償があったとも解釈できる。
夜の明積寺に立てば、母の影が飴を求めてさまよい続けている気配を感じる者も少なくない。
飴買い幽霊の伝承は、単なる昔話ではなく、今もなお生き続ける心霊現象であるといえよう。
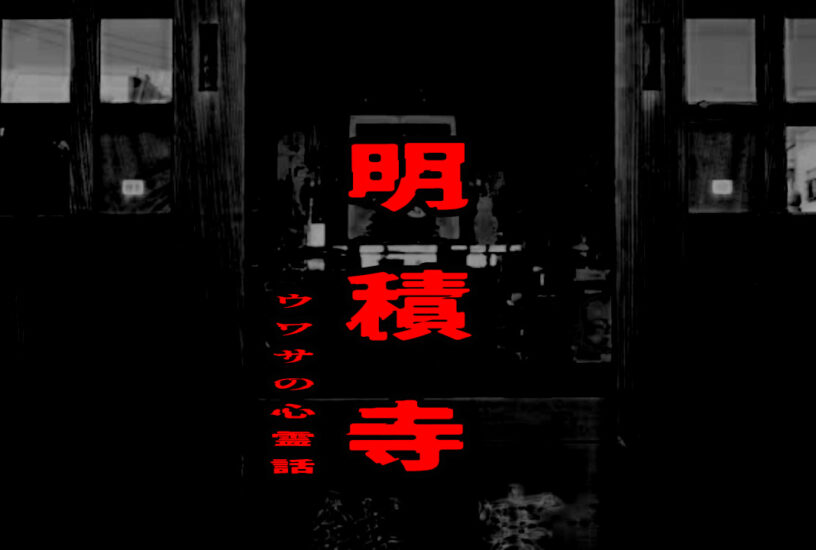
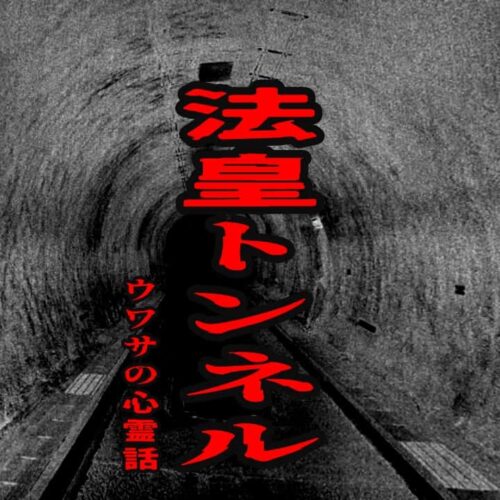
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
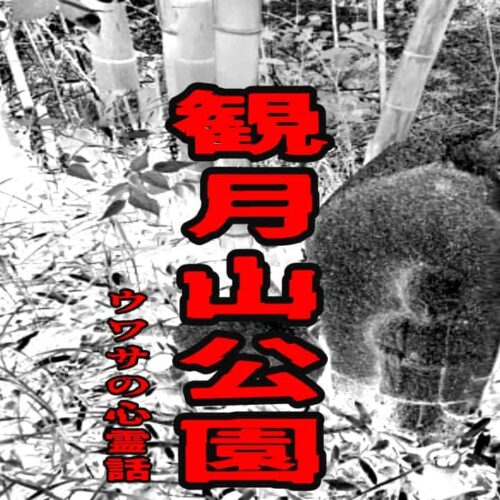

のウワサの心霊話-500x500.jpg)
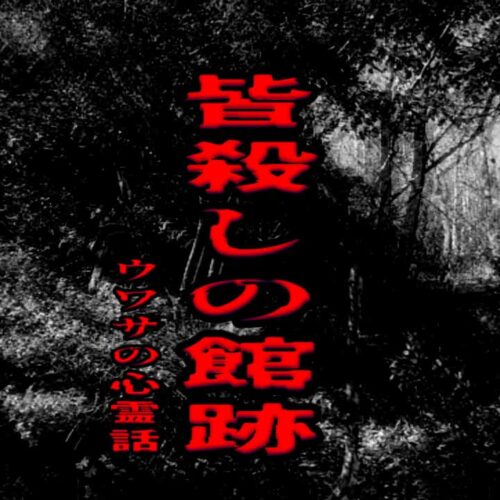
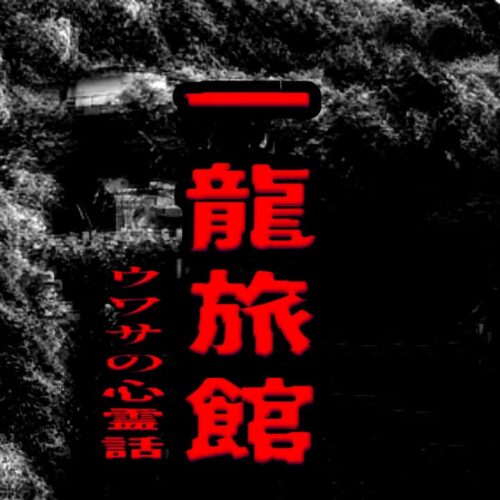
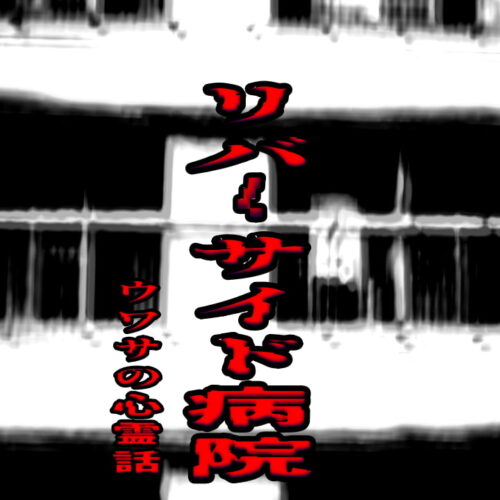
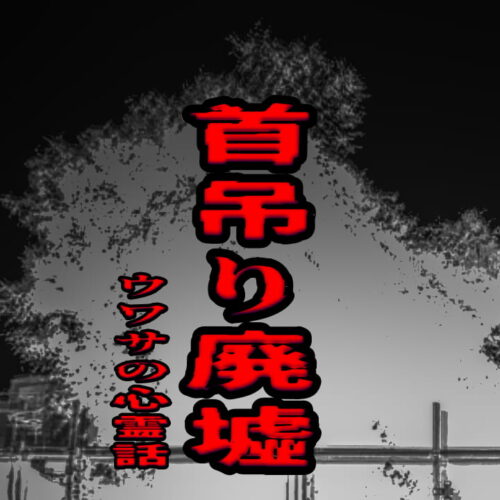
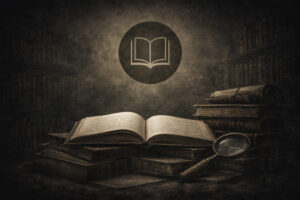
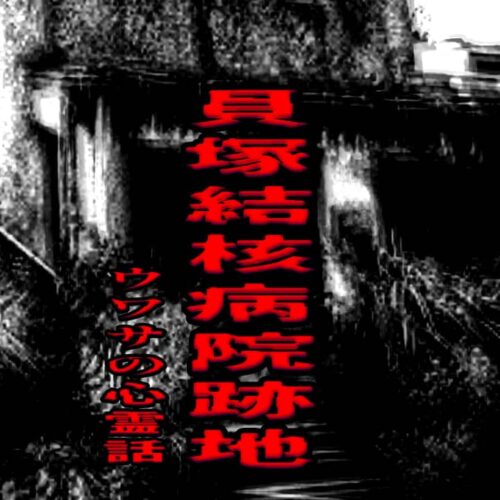
コメント