愛媛県西条市にある船山古墳群は、古墳時代後期に築かれた群集墳であり、かつて豊臣秀吉の四国征伐の戦場ともなった場所である。今回は、船山古墳群にまつわるウワサの心霊話を紹介する。
船山古墳群とは?

船山古墳群は、愛媛県西条市小松町新屋敷に位置する県指定史跡である。
中山川が燧灘に注ぐ河口近くの独立丘陵に築かれており、古墳時代後期に造られた群集墳である。
丘陵は東西300メートル、南北100メートル、高さ15メートルほどで、船の形に似ていることから「船山」と呼ばれている。
丘陵の東部には三嶋神社が鎮座しており、西部にはかつて20基ほどの古墳が築かれていたと伝わる。
現在確認できるのは10基程度であるが、その多くは破壊や風化により形を失いつつある。
嘉永7年(1854)の神社遷座の際には石棺や人骨、武具、勾玉などが出土しており、現在も一部は東京国立博物館に収蔵されている。
古代からの眠りを破られた土地であるがゆえに、数々の不気味な噂が絶えないのである。
船山古墳群の心霊現象
船山古墳群の心霊現象は、
- 深夜になると戦をしているような声が聞こえる
- 静寂の中で人の囁きがかすかに響く
- 強い霊感を持つ者が「嫌な気配」に襲われる
- 古墳群を歩くと背後から誰かに見られている感覚に陥る
である。以下、これらの怪異について記述する。
この地には豊臣秀吉の四国征伐の際、多くの武将が血を流した戦場の記録が残されている。
そのためか、古墳群を夜に訪れると「鬨(とき)の声」や「武者の怒号」のような音が風に紛れて響いてくると語られている。
また、霊感を持つ者は、古墳群に足を踏み入れた瞬間から重苦しい圧迫感を覚えるという。
まるで見えない兵たちが未だに武具を携えて徘徊しているかのように、肌が粟立ち、背後から視線を感じるのである。
特に丘陵西部の花陵神社付近では、かすかな囁き声が耳にまとわりつくという証言もある。
誰もいないはずの古墳群で聞こえるその声は、戦に散った武士の怨念か、それとも古墳に眠る魂の呻き声であろうか。
船山古墳群の心霊体験談
ある地元住民は、深夜に古墳群を横切った際、耳元で「やめよ」「退け」といった言葉を囁かれたと証言している。
振り返っても誰もいなかったが、その後も一定の間隔で声が追いかけてくるように聞こえ、恐怖のあまり全力で駆け下りたという。
また別の人物は、古墳群の斜面で立ち止まった瞬間、複数の足音が砂利を踏むように迫ってきたのを感じたが、後ろを見ても誰一人としていなかったという。
以後、その人物は二度と船山古墳群に近づくことはなかったと語っている。
船山古墳群の心霊考察
船山古墳群の怪異は、古墳という「死者を葬る場」と、戦乱の血で染められた「戦場」という二重の怨念が重なり合うことで生まれていると考えられる。
古墳に眠る魂は本来静かに祀られるべきであった。
しかし、嘉永年間の神社遷座で副葬品や人骨が掘り出され、その安寧は破られた。
さらに、四国征伐で倒れた無数の兵の無念が土地に染み付き、今もなお夜な夜な声や気配として現れているのだろう。
表立った怪奇現象は少ないが、霊感の強い者ほど強烈な圧迫感や囁きを体験していることから、この地は「静かに眠る者の怨嗟が溶け込んだ場所」であるといえるかもしれない。
訪れる際には決して軽い気持ちで立ち入るべきではないであろう。
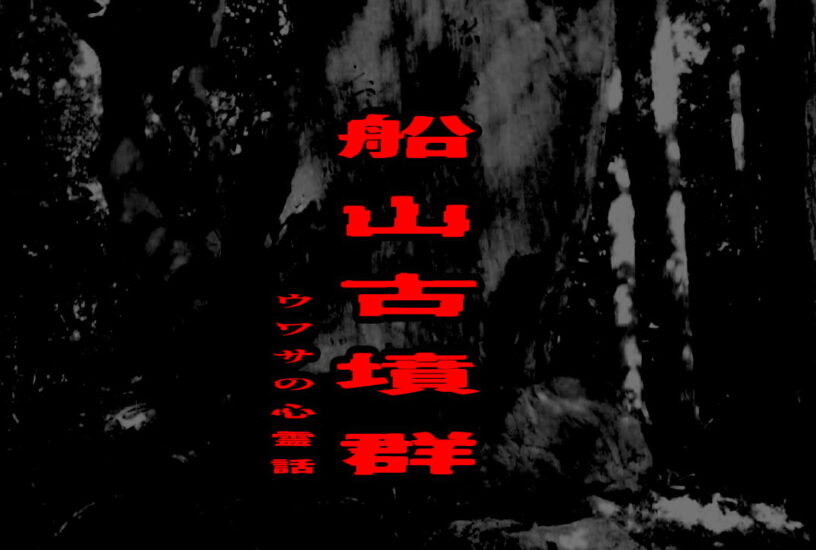

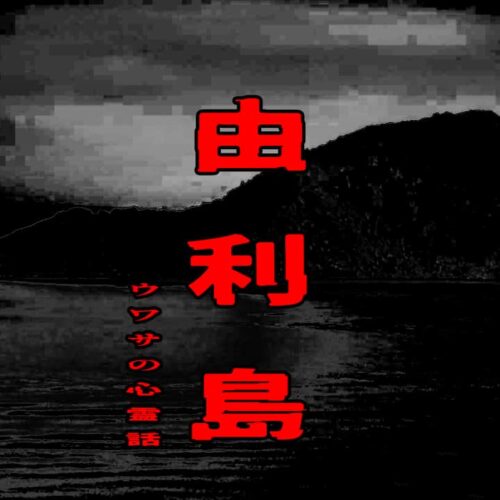
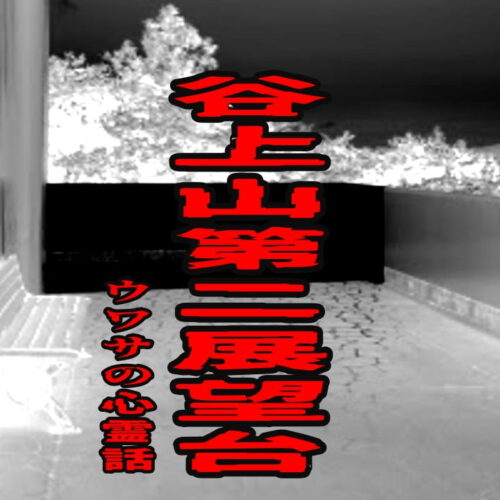
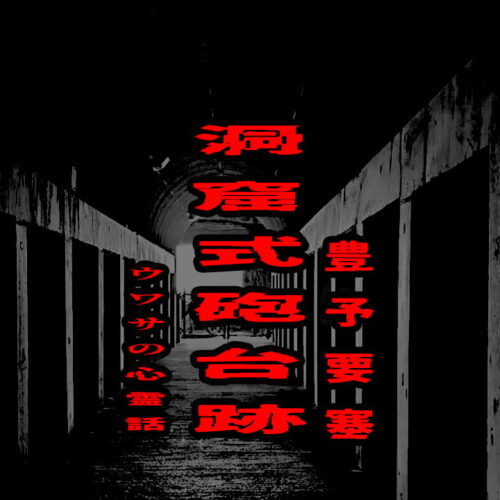
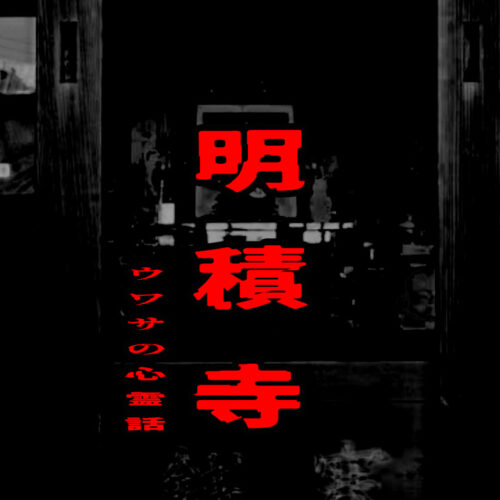
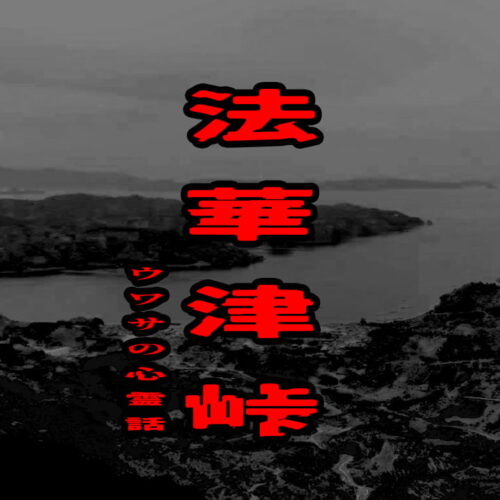
のウワサの心霊話-500x500.jpg)
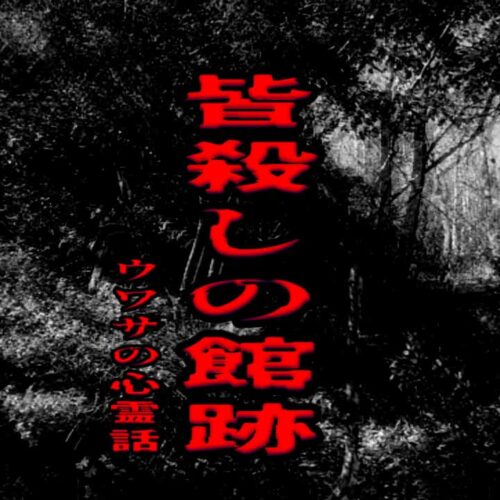
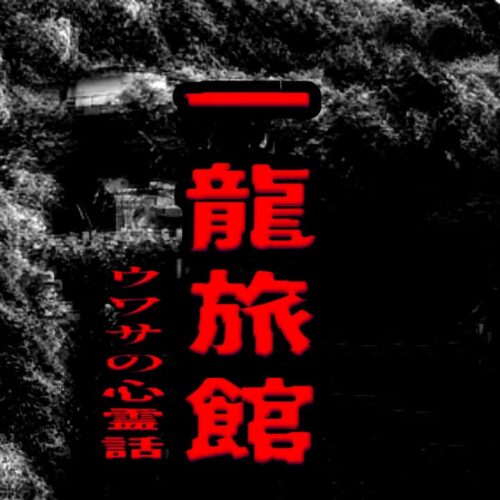
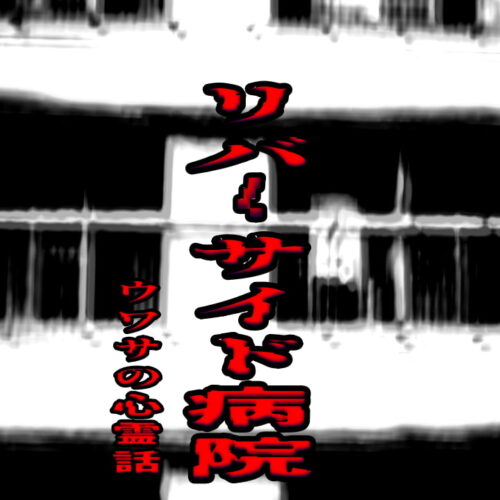
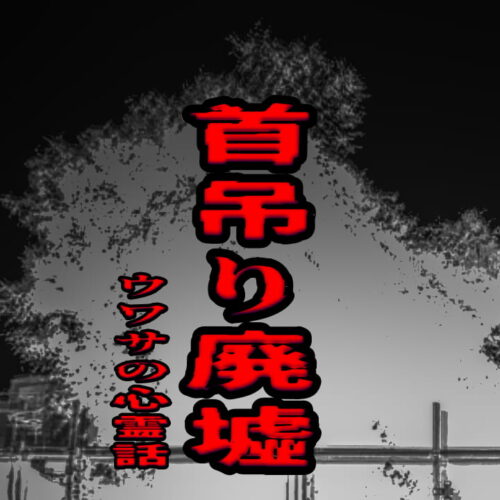
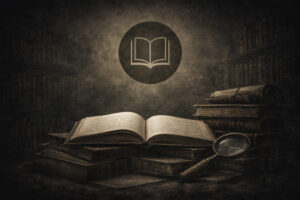
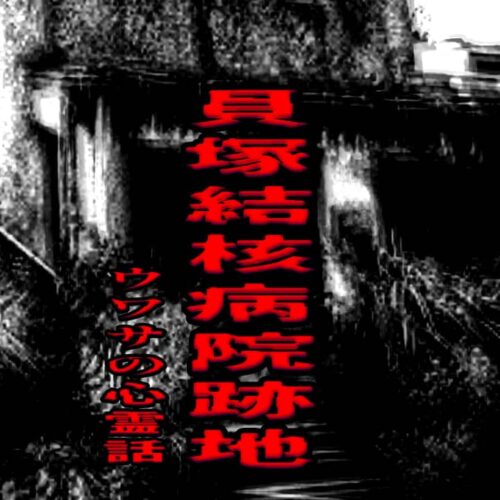
コメント