お正月は新年を祝う明るい行事ですが、その裏には意外な側面がある。実は、お正月に拝んでいるのは「死霊」だという説があるのだ。民俗学によれば、正月は「この世」と「死者の世界」の境界が曖昧になる特別な時期であり、死霊が帰ってくるとされている。この記事では、お正月の知られざる意味とともに、三が日でやる4つの怖い意味について詳しく解説する。
お正月に拝んでいるのは死霊
結論からいえば、お正月に拝んでいるのは「死霊」で、民俗学で有力な説に基づいている。
正月は日本人にとって新年が明けることであり、「この世(現世)」と「死者のいる世界」の境目が曖昧になることでもある。
亡くなった者の「死霊」が死者のいる世界「山」や「異界」から、里や街へと帰ってくる「特別な時間」であるらしい。
地方により正月に訪れる者は違いがみられるが、ほとんどの伝統の中で正月には「死霊」が来るという特徴がある。
古くは、正月には「死霊」を迎える時間であり、初詣は「死霊」に向かい合う時間であった。
江戸時代には、一家の長男は何日も冷水を浴びるという修行をしなければならず、新年を厳粛に迎えていた。
お正月とお盆は、むかしの日本では同じような意味があって、本来は祖霊を迎えるめでたい日ではなかったかと思われる。
— 生きる知恵bot (@ikiruchiebot) August 21, 2022
迎火、送火、盆舟、送り舟などの民俗も、仏教的というより、古い日本の習俗に根ざしている。
(お盆/第三号)
死霊を蘇らせるための鏡餅
鏡餅は、新年の神様である「年神様」の依り代で、捧げるものとして云われてる。だが、その一方、「お正月に訪れる死霊を蘇らせるもの」という意味もあるという。
鏡餅は、神様が宿る依り代であるが、この神様こそ死霊のことだという。そのため、お正月は、「死霊を迎える儀式」だとも云われている。
年神様とは、過去に亡くなった人のことであり、死霊である。お正月は、その死霊を迎える儀式であるという話である。
依り代の鏡餅には死霊が宿るのだが、その鏡餅を食べるのが「鏡開き」で、死霊を宿らせた餅を食べる儀式だったのだ。
もちろん、年神様であるから悪霊のようなものではないらしい。
【PR】
お正月はお葬式
お正月は明るいイメージが強くあるが、現在でもお正月には死霊を祀り共に過ごすという意味がある。
お正月には家に帰り家族と共に過ごす者は多くいるはずだ。その際には、和服などの綺麗な服を着ることもある。
これは、意識をしていなくても「死霊の祭り」として新年を迎える「葬式」のようなものであるという。
新年は「歴がはじめに戻る」つまり「新しく世界が始まる」ということを意味しており、生と死の境目も曖昧になる時なのだ。
このような儀式は世界各地であり、例えばメキシコで知られる「死者の日」では、10月31日の真夜中に先祖が家族がいる現世に戻ってくると信じられている。
11月2日にはラテンアメリカの諸国で盛大に行われる「死者の日」があり、日本のお盆のような行事となっている。家族や友人等が集まり、お酒や食べ物を持ち寄り墓に集まり盛大な祭りが催される。
このような伝統はヨーロッパでも見られている。
そう言えば葬式の時に御坊さんが「37回忌(?)までは仏様だから、お彼岸に帰ってくるんだけど、それ以降は神様になるからお彼岸じゃなくてお正月に帰ってくるんだぜ」とか言ってたけど、本当か? 神仏習合にしても、ちょっと意味不明じゃないか。仏さんから神様に進化とかしないのでは? するの?
— karakumoP (@ku_mo_ra) October 1, 2012
悪霊を追い払う門松
お正月に玄関先に飾られる門松だが、「死霊(年神様)」の目印とされている。死霊といえど、さまざまな霊がいるため、招き入れる霊は悪霊であってはならない。
門松を玄関に置くことで良い霊だけを歓迎し招き入れる役割がある。門松の竹は、武器を意味し、松は良い霊のため(神様のため)のものである。
お正月に彷徨っている悪霊を追い払う武器として門松があり、家族を守る役目がある。
一説におせちには、死霊に食べて頂き、その食べたおせちを食べることで霊力を得るという意味もあるようだ。
お正月を迎える際には、死霊である年神様だけを招けるよう鏡餅や門松など準備してお正月を迎えるのがいいだろう。
【PR】
正月三が日のタブー
正月三が日には、家庭や家事に関するいくつかのタブーがある。これらの習慣は昔の知恵や文化に由来し、良い年を迎えるためのヒントとなるので覚えておくといい。
- 掃除
三が日に掃除をすると、年神様が追い出されてしまうと云われている。特に掃き掃除は避けられている。12月31日に「掃き納め」をして、新年を迎えるための準備を整える。
- 洗濯
水の神様に休息を与えるために洗濯を避ける習慣がある。また、年神様から得た福を流してしまうという考えも。
- 火や刃物を使った料理
火の神様である「荒神様」が火を使うことを好まず、激しい性格のため新年早々は避けられる。また、刃物を使って縁を切るとされ、料理をすることも控えられている。
- 四つ足動物の肉を食べない
牛や豚などの四つ足動物の肉を忌避する文化があり、おせち料理には魚が中心に使われる。肉を使う場合には鶏を選ぶことが一般的。
- 無駄遣いをしない
新年に浪費するとその年の貯蓄が減るとされ、無駄遣いを避ける習慣がある。ただし、お賽銭やお年玉は例外。
- けんかを避ける
新年早々のけんかや悪口は、その年の不和を招くとされている。睦月(むつき)は家族や親戚との和やかな時間を過ごすことに由来する。
これらの習慣は古くからの知恵や思いが反映されている。
気にする人は少なくなっているが、良い年を迎えるヒントとして参考にしてみるといいだろう。
【PR】




-500x500.jpg)


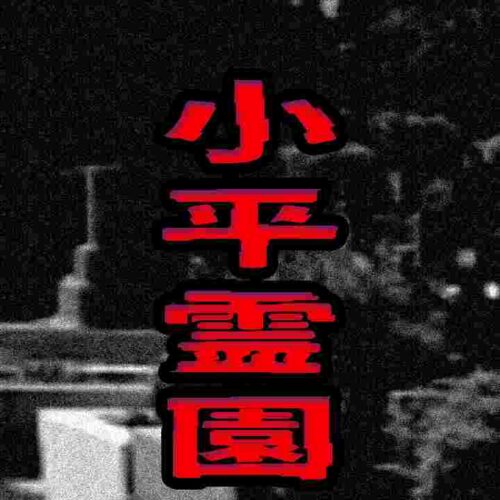
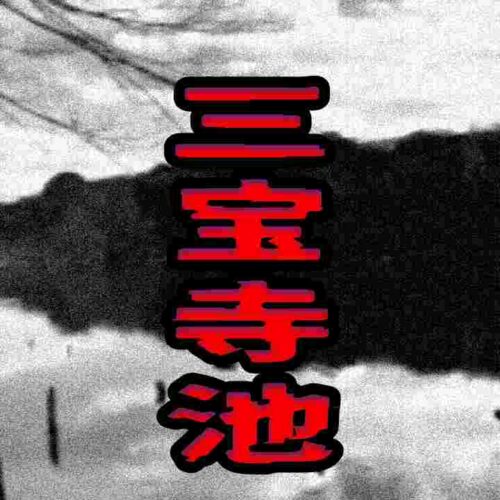
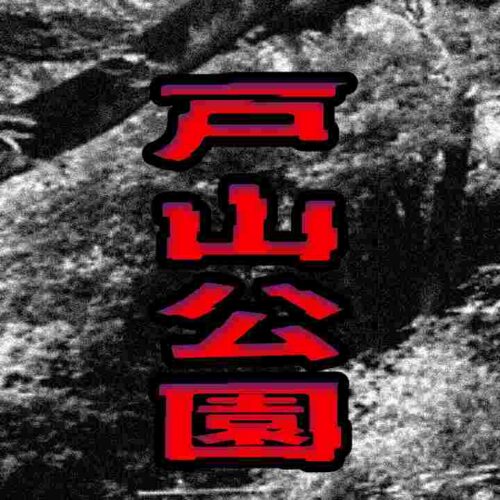

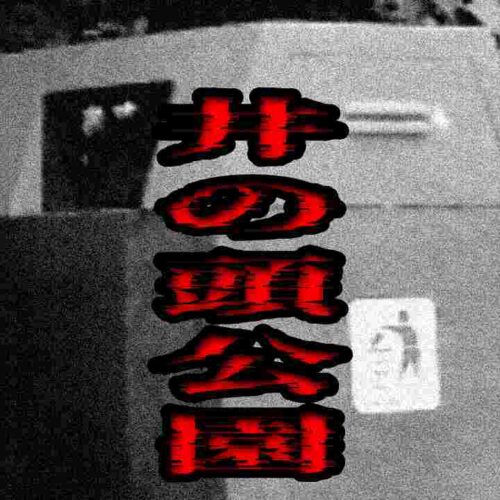
コメント